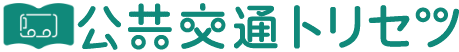担当:井原雄人(早稲田大学スマート社会技術融合研究機構)

トリセツを読んで始めたのに、自分たちのバスの利用者が増えません。騙された!
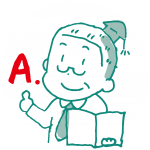
大変申し訳ございません。必ず上手く方法があれば困っている地域はもうなくなっているでしょう。騙されついでに、もう1つ試してみませんか?
しっかり考えて始めたはずなのに
始める前に公共交通が提供する6つのサービスとは何でしょうか?の記事をよく読んで、利用促進についても公共交通の利用促進に取り組むために、コミュニティバスの利用者増には何をしたらいいですか?、利便性の向上と利用促進の関係も読みました。一緒に乗って利用者の声も聞いてみましたが、大きな不満も無いようで、どうしたらよいか分かりません。
トリセツに書いてある通りにやれば、必ず上手くいくというわけではありません。地域の事情に合わせて常に試行錯誤していくことが必要です。
「利用者」の声を聞いてみても問題がないのであれば、何かしらの理由で「利用しない」人に問題があるのかもしれません。例えば分かりやすい理由として、バス停まで歩けないというものがあります。これに対しては定時定路線ではなく、オンデマンド交通やタクシーの活用という異なる形態のサービスが必要となります。走ってるのを知らなかったというのであれば、広報や案内の充実が必要です。これらのことは、しっかり記事を読んでいる方ならすぐに気が付くでしょう。
しかし、利用していない人の声が思い込みということもよくあります。そして、その思い込みの中でよくあるのが「バスは不便」というものです。しっかり考えて便利なサービスを作ったのに「便利なことも、体験してみなければ分からない」というところに問題があるかもしれません。
1回目の体験の作り方
「体験してみなければ分からない」という問題に対する対策はとても簡単です。体験する機会を作ればよいのです。簡単に取り組めるのは、日を決めてみんなでお買物や食事に行くというのはどうでしょうか。みんなの範囲は様々で、ご近所に声を掛けるという方もいれば、町内会が呼びかけてという形でも構いません。クルマ1台に乗れないくらいの人数を目指すと、公共交通を使う理由にもなるのでよいかもしれません。
どんなに考えられたサービスでも、クルマの方が便利ということがほとんどです。クルマより便利な体験ということではなく、公共交通でも「まぁ、これでもいいか」という便利さや意外に便利だったというを体験してもらうぐらいの気持ちで取り組みましょう。また、公共交通で行くからこそ得られる「みんなでおでかけする」という体験をより楽しめるように、積極的に車内でおしゃべりをしたり、買い物先でお茶をするというようなものと組み合わせるのもよいかもしれません。いわば公共交通を活用したお買い物ツアーです.
いろいろな方法での1回目
声をかけたら/かけられたら参加するというのは、簡単だと書きましたが奥ゆかしい方はそれも難しいという方もいるかもしれません。そんな方には少し極端ですが、「お当番制」や「お声がけ」のような取り組みをしている地域もあります(あえて匿名です)
お当番制
ある地域でコミュニティバスの実証試験が行われました。1便10人の乗車を目標に、この目標を達成したら本格運行に移行するという計画でした。しかし、導入されたら乗るのにと言っていたはずの住民はあまり乗車せず、結果は5人に満たない人数でした。「典型的な乗る乗る詐欺」の事例です。
目標を達成できなかったので、本格運行は行われないはずでしたが、地域からは泣きのもう1回が入りました。そして、後がなくなった地域ではお当番制による乗車を始めました。「月曜日は○○さん、火曜日は○○さん」のように乗車するお当番が回ってくるのです。ここだけ切り出すと無理やり乗せて運行を続けようと取り組みになってしまい、あまりよいものとはいえません。
しかし、この地域でのポイントが2つあります。1つ目はお当番が回ってくるのは半年に1回、2つ目は今回のテーマである1回目の乗車体験のきっかけになったというところです。
半年に1回というのはいつも満員になるように、高頻度にお当番を設定するのではなく、「仕方ないか」と思ってもらえる範囲で設定しました。ごみ集積場の周りの掃除も毎週回ってくると大変ですが、たまになら地域のために仕方ないと思ってやるのと同じイメージです。
そして、1回目のきっかけというのは、お当番制により初めて乗車した人が「まぁ、これでもいいか」と思ってくれて、その後も利用するようになってくれたということです。具体的には、今まで自分で運転して通勤してるときにはできなかった、読書や疲れているときには寝てれば到着するという価値に気が付いて、お当番以降も乗車するようになりました。
この結果、2年目の実証試験では利用者は1便10人を上回り、その後同じように価値に気が付いた人が増え、1台では乗り切れないために増便するというようなことまでおきました。
お声がけ
別の地域では、地域が主体となって行われている互助輸送があります。ある日いつものように運行していると、荷物をもって大変そうに歩いているおばあさんがいました。それを見かけた運転手さんはおばあさんの隣で停車して「乗っていきませんか?」と声をかけたのです。
このバスはルート上で手上げ式で乗降できるルールですが、この場合はおばあさんが手を上げたわけではないので、少し微妙なお話です。運転手さんには手を上げたように見えたのでしょう。
声をかけてもらって乗車したおばあさんは「バスが走ってるのは知っていたけれど、どうやって乗ったらいいのか分からなかった。」とのことでした。しかし、1回乗ってみるととても便利なことが分かり、今では毎日のように乗ってくれる常連さんになりました。
この地域では全戸に回覧板でバスの乗り方の案内をしていました。しかし、紙で見るだけでは分からないこともあり、実際にやってみようとすると不安もあります。案内だけでなく、一緒に手を上げてバスを停めてみるという体験会をしてみるのもよいかもしれません。
2回目も乗る人の割合
ここまで1回目のきっかけが大切だと書きましたが、全ての人が2回目も乗ってくれるわけではありません。むしろ乗ってくれない人がほとんどということも少なくないでしょう。 そもそも地域の中では公共交通を利用する人の割合の方が少ないというのが一般的です。例えば100人の村で、公共交通を利用する人が10人、利用しない人が90人いたとしましょう。公共交通を利用する人が1割いるというのは、過疎地ではこれでも多い割合です。利用しない90人に1回目のきっかけを提供し、その中の1人(1%)でも利用する人に転換してくれれば利用者は11人になるので、1.1倍です。何もしなければ減っていくばかりの利用者数が1.1倍になるというのはすごいことだと思います。
9割の人の中には、本当は常連客になってくれそうな人がいるのに取りこぼしているかもしれません。1回目のきっかけづくりをできるだけ幅広く行うことで、移動手段があることの価値を広めていきましょう。こうした取り組みこそが、人々の行動変容を促すという意味でモビリティ・マネジメントといえるのだと思います.