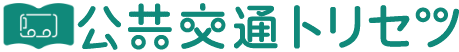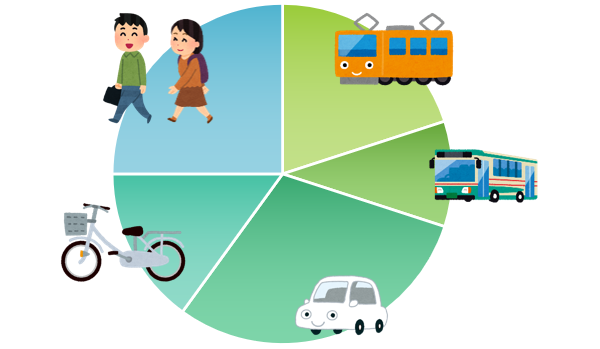パーソントリップ調査とはなんですか?
担当:西堀泰英(大阪工業大学)
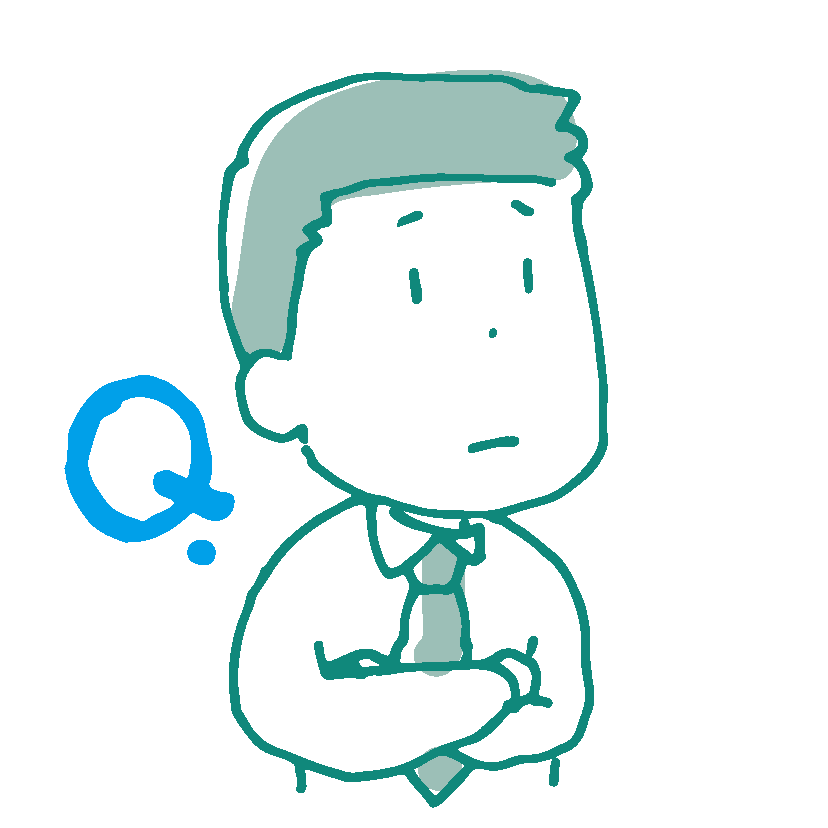
ときどき「パーソントリップ調査」のことを目にします。どんなことがわかるのですか?
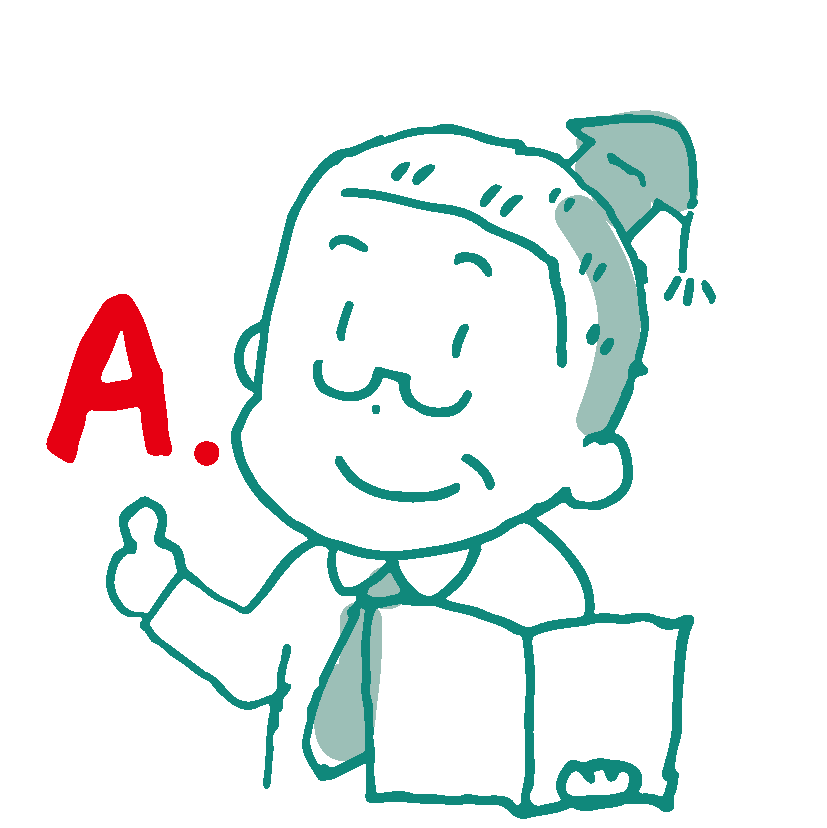
都市や地域における人々の移動の実態がわかります。人々の移動の回数(「トリップ」と言います)、一人ひとりが行う個々の移動の目的、交通手段、出発地と到着地、移動の時刻、移動する人/移動しない人の年齢や職業などの個人属性など、交通計画を作るために必要で、貴重な情報を得ることができます。
はじめに
突然ですが、問題です。
問題1 あなたがお住いの地域の住民のうち、1日のうち1度でも外出する人は何%ですか?
問題2 あなたがお住いの地域の65歳以上の高齢者が、1日のうちに移動する回数は平均して何回ですか?
問題3 あなたがお住いの地域の運転免許を持たない住民が利用する交通手段のうち、最も多い手段は何ですか?
問題4 あなたがお住いの地域の中で最も多くの人が買物に訪れる場所はどこですか?
すぐに答えが出てきたあなたはとても物知りですね。でも、答えられなかったとしても、気にすることはありません。トリセツ読者の皆さまの中には、答えが出てこなくても答えを求める方法をご存じの方もおられるかもしれません。そうです。これらのことは「パーソントリップ調査」の結果から知ることができます。
パーソントリップ調査の結果は、パンフレット、報告書、集計データなど様々な形で見ることができます。どこを見れば何がわかるかを知っていれば、交通計画を行う際にとても強い味方です。上のクイズも、地域の範囲の取り方にもよりますが、問題1の答えはいとも簡単に、問題2、3の答えは比較的簡単に知ることができます。
さて、以降では、使い方がわかればとても役に立つパーソントリップ調査について、公共交通にかかわりのある皆さまに知っておいて欲しいことを紹介したいと思います。
どんな調査ですか
(1)パーソントリップ調査データの特徴
パーソントリップ調査については、国土交通省都市局のホームページをはじめ、調査を実施する行政機関のサイトなどで説明がなされています。
例えば国土交通省都市局ホームページでは、
「どのような人が、どのような目的で、どこから どこへ、どのような時間帯に、どのような交通手段で」移動しているかを把握することができます。と紹介しています。この説明は様々な場面で目にすることができます。なお、人々の移動を目的ごとに集計する単位を「トリップ」と言います。だからパーソントリップ調査は人々のトリップを把握することを目的とした調査です。
筆者としては、上の説明にさらに付け加えたいと思います。それは、老若男女、特に10代以下や80代以上の年齢層の状況、トリップの目的や利用した交通手段、そして外出していない人の状況も含めて、一定の統計的精度を持って把握することができる、ということです。
この特徴は、いわゆる人流ビッグデータの多くが持たない、パーソントリップ調査データが持つ優れた点であると言えます。これらの優れた点は、自治体の全ての住民を対象とする行政の計画(例えば、地域公共交通計画)を策定する際に、重要であると言えます。一方、人流ビッグデータが優れる点もあります。それは、時系列的(継続的)、かつ、即時的、そして比較的微視的に捉えることができる点です。この点は、社会の変化が激しい昨今においては、重要な点であると言えます。そのため、都市交通調査ガイダンス(令和6年6月版)では、パーソントリップ調査と人流ビッグデータのそれぞれを相互補完や融合して活用する考え方が提案されています。
なお、人流ビッグデータとパーソントリップ調査データの違いについては過去のトリセツ記事「人流ビッグデータにはどのようなものがありますか?」で詳しく整理されていますので参照してください。
(2)パーソントリップ調査の実施状況
国土交通省の情報によると、パーソントリップ調査は65都市圏、延べ151回実施されています(令和6年(2024年)3月時点)。実施都市の地図を図1に示します。これを見ていただくとわかるように、全国津々浦々とまでは言えませんが、各地で調査が実施されています。なお、図1の丸印は調査対象圏域の範囲を示すものではないのでご注意ください。なかでも三大都市圏と言われる東京都市圏、近畿圏(京阪神都市圏)、中京都市圏は、特に広い範囲を対象地域とした調査が行われています。パーソントリップ調査の調査圏域は主に通勤圏をベースに決められているので、大都市圏は広域になるのです。
このように数多くの都市圏で実施されてきたパーソントリップ調査ですが、各都市圏における実施回数は1回から6回までばらつきがあります。先ほど出てきた三大都市圏は、1970年前後から10年に1回の頻度で、これまでに6回調査が実施されてきました。地方都市圏では過去に1度しか実施されていない都市圏も珍しくありません。こうした地域では、交通計画を検討する際には、小規模で簡易なパーソントリップ調査や、先述した人流ビッグデータ等を活用して、地域の移動実態を把握することが求められます。
図1 パーソントリップ調査の実施都市
出典:国土交通省都市局ホームページより
(3)調査の方法とデータ使用時の注意点
パーソントリップ調査は、多くの場合一人で移動することが想定される5歳以上の住民全員を対象に、対象圏域の自治体にお住まいの世帯を無作為に抽出して行われます。回答者に年齢や地域の偏りが生じないよう「無作為に抽出」していることが、パーソントリップ調査の優れた点につながっています。
ここで、「抽出」について説明したいと思います。人々の移動実態を調査する際、対象地域の居住者全員を対象に調査を行うことができれば高精度に把握することができますが、莫大な費用が掛かりますし、交通計画を検討するにあたってそこまでの精度は必要ありません。そこで、対象地域の居住者(母集団と言います)の統計的な特徴を把握するのに必要な数の居住者を抽出して調査対象とします。全居住者から調査対象者を抽出する割合を「抽出率」と呼びます。例えば、20万人が居住する都市圏において1万人の回答を得る場合の抽出率は、10,000人÷200,000人=0.05(5%)となります。
具体的な例を紹介します。令和3年(2021年)に実施された第6回近畿圏パーソントリップ調査では、人口の約1.0%の抽出によるサンプル調査です(京阪神都市圏交通計画協議会HP)。第6回近畿圏パーソントリップ調査では、1%の抽出率で得た調査結果を都市圏全体の移動データとして扱うことができるように、1人の移動データを平均して約100倍(拡大係数)に拡大して作成されています。1つのトリップが100回になるわけですから、サンプル数の少ないエリアなどでは、データを観る際に抽出率や拡大係数を確認することは、データを見誤らないために必要なことです。
こうしたことから、パーソントリップ調査データには一定の誤差が含まれることに注意が必要です。ちなみに、平成22年(2010年)に実施された第5回近畿圏パーソントリップ調査の抽出率は約3.5%であり拡大係数は約30倍でした。このように抽出率や拡大係数は、調査によって異なるため、パーソントリップ調査データを使用する際は確認することをお勧めします。
パンフレットや報告書に掲載されているデータは通常、一定の精度を持つデータであると言うことができ、誤差を気にする必要はあまりないでしょう。しかし、後述するマスターファイルと言われる調査結果のデータベースを用いて独自に集計する際は、集計結果の精度に注意することが求められます。
なにがわかるのですか
パーソントリップ調査でわかることは、すでにいくつか記載してきました。ここでは、筆者のホームグラウンドである近畿圏の最新調査データとその推移を紹介する形で、具体的な例を示したいと思います。
(1)居住者の総移動回数(生成量・総トリップ数)
図2は、都市圏居住者が行う総トリップ数と総人口の推移を示したものです。令和3年(2021年)における近畿圏(時系列比較のために第3回調査圏域内での集計)の総トリップ数は1日あたり3,427万トリップでした。第5回(平成22年(2010年))と比べて減少しています。トリップ数のピークは平成12年(2000年)であり、新型コロナウィルス感染症の感染拡大による外出自粛等も影響していると思われますが、トリップ数は10年で9%程度ずつ減少していることがわかります。総人口の変動に比べて、トリップ数の変動が大きいことがわかります。
そして、このグラフには推計値として令和12年(2030年)と令和22年(2040年)の値も示されています。これは、将来人口推計値を用いて将来のトリップの状況を推計した結果です。人口が減少するにつれてトリップ数も減少していることがわかります。
なお、令和12年(2030年)以降の推計値は、令和3年(2021年)の状況を前提としているので減少幅が小さくなっていますが、あくまでも推計値であり推計の前提によって変動します。そのため今後は減少幅が小さくなると楽観することは禁物です。この理由については、今後の記事で改めて触れたいと思います。
このようにパーソントリップ調査は、過去との比較が可能であるとともに、将来の推計を行うことで、将来の移動の状況を見通すことも可能です。
図2 総トリップ数と総人口の推移
(2)居住者のうち外出した人の割合(外出率)
図3は、都市圏居住者のうち外出した人の割合(外出率)の推移を示したものです。昭和55年(1980年)をピークに減少し続けていますが、平成12年(2000年)以降、減少幅が大きくなっています。令和3年(2021年)には、平均して100人のうち74人が外出し、26人は外出していない状況にあると言えます。
図3 外出率の推移
(3)1人あたりのトリップ数の平均値(生成原単位)
図4は、都市圏居住者の1人あたりのトリップ数の平均値の推移を示したものです。ここで「夜間人口あたり」と「外出人口あたり」がありますが、前者は外出率の減少の影響も加味された値です。いずれも、昭和55年(1980年)をピークに減少し続けていますが、平成12年(2000年)以降、減少幅が大きくなっています。
令和12年(2030年)以降の推計値は横ばいの傾向にあります。繰り返しになりますが、これをもって将来を楽観することは禁物です。
図4 一人あたりトリップ数の推移
(4)交通手段別のトリップの割合(交通手段分担率)
図5は、交通手段別のトリップ数の推移を示したものです。令和3年(2021年)時点で交通手段分担率が最も大きい手段は自動車の31.4%であることがわかります。昭和55年(1980年)に目を向けると、徒歩(37.6%)が最も分担率が大きい手段であったことがわかります。
また、鉄道トリップに着目するとの分担率は、平成22年(2010年)から令和3年(2021年)にかけてトリップ数は減少していますが、分担率はわずかですが分担率が上昇(20.3%→21.2%)していることがわかります。鉄道だけでなく自動車のトリップ数も減少しています。こうした変化が生じている要因がわかれば、公共交通のさらなる利用促進や活用につなげることができるかもしれません。パーソントリップ調査データはそうした分析にも活用できます。
図5 代表交通手段別トリップ数の推移
(5)移動目的別のトリップの割合
図6は、移動目的別トリップ数の推移を示したものです。令和3年(2021年)は出勤目的トリップが増加しています。この背景には女性の社会進出等の影響が指摘されています。一方業務目的は大きく減少しており、この背景にはWeb会議の普及等が指摘されています。
令和12年(2030年)では、少子化の影響により登校目的トリップが大きく減少し、高齢化の影響により自由目的トリップの割合が大きくなっています。このように、パーソントリップ調査は、個人属性を考慮した分析や推計を行うことができます。
図6 移動目的別トリップ数の推移
どうしたら使えますか
これまでに紹介してきた第6回近畿圏パーソントリップ調査のデータは、出典資料に示しているパンフレットをご覧いただけば、確認することができます。パンフレットには、基本的な調査結果が掲載されています。ほかの都市圏においても、パーソントリップ調査結果を取りまとめたパンフレットや記者発表資料がインターネット上で公開されている場合が少なくないので、一度調べてみてはいかがでしょうか。
パンフレット以外に公開されている情報に、集計結果があります。これは、パーソントリップ調査データを集計して得られるもののうち、利用頻度が高いものをあらかじめ集計し、インターネット上で公開しているものです。利用目的の登録など簡単な手続きを踏むだけで利用できる場合があります(都市圏により異なります)。
このほか、Web上でパーソントリップ調査データを任意に集計することができるシステムを公開している都市圏もあります。この集計システムを用いると、より自由度の高い集計を行うことができます。また、マスターデータは、パーソントリップ調査の個票データであり、全ての集計に用いる元となるデータです。エクセル等の表計算の知識が一定程度あれば取り扱うことができますが、統計法や統計調査情報条例等に則って適切に扱うことが必要となります。
なお、本稿の冒頭に示した問題4の値は、集計システムやマスターデータを使用して求めることができます。
表1 パーソントリップ調査データの提供方法の概要
| 種類 | 概要 | 備考 |
| パンフレット | 基本的な集計結果が図表やコメントと共に掲載したもの | PDF等で公開している都市圏が多い |
| 集計結果 | 利用頻度の高い集計結果をあらかじめ集計したもの | ゾーン別の集計など、比較的細かい集計結果が使用できる 三大都市圏の集計結果は、国土数値情報にも掲載されている |
| 集計システム | Web上でパーソントリップ調査データを任意に集計することができるシステム | 提供している都市圏は多くないが、より自由度の高い集計を行うことができる |
| マスターデータ | パーソントリップ調査の個票データであり、全ての集計に用いる元となるデータ | 統計法や統計調査情報条例等に則って適切に扱う必要がある |
おわりに
本稿では、パーソントリップ調査のことをあまり知らない人に向けて、パーソントリップ調査データを使ってどんなことがわかるか、どのように使うことができるか、を紹介しました。途中、少し細かいところにまで踏み込んで書いた部分もありますが、多くはパーソントリップ調査データを扱う人には知っておいていただきたいことですので、参考にしていただければ幸いです。
パーソントリップ調査データは、地域の公共交通の検討を行う上でたくさんの有用なデータを提供してくれます。ぜひ一度使ってみてください。でも、地域の公共交通のことを考えるために大事なデータであることはわかっても、なかなかとっつきにくいなぁと感じる人も多いかもしれません。そういう人は、お住まいの地域や仕事で関わりのある地域で、過去にパーソントリップ調査が行われたのかを調べてみてください。そしてもし調査が行われていれば、最新のデータは何年のものか、外出率や生成原単位や自動車分担率はどれくらいか、を調べてみてください。まずはそこから始めてみてはいかがでしょうか。
パーソントリップ調査データを扱うことで、ここで紹介したこと以外にも、様々なことを知ることができます。今後のトリセツの記事でも取り上げて紹介していきたいと思います。