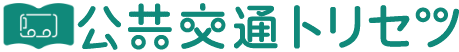担当:トリセツ編集会議
北陸信越運輸局交通企画課長である新倉さんへのインタビュー最終回です。今回な地方運輸局「活用のススメ」についてお話しいただきます。
前々回の記事「新倉課長に聞く!<1> 運輸局・運輸支局ってどんな組織?」
前回の記事「新倉課長に聞く!<2> 国の補助制度ってどう使ったらいいの?」
地方運輸局「活用のススメ」
<編>:これまで「地方運輸局」「国の予算」について伺ってきましたが、最後に、新倉課長からのリクエストにより、地方運輸局「活用のススメ」と題して、主に自治体職員の方を念頭に、地方運輸局を積極的に「活用」するためのポイントを紹介いただきます。
<新>:地域公共交通分野において、地方運輸局には大きく4つの強みがあると思っています。
1:道路運送法、地域交通法等の関係法令・通達に精通している【制度面のノウハウ】
2:補助金に関するメニュー・要件に精通している【補助金面のノウハウ】
3:許認可・監査権限を通じた、交通事業に関する知見【交通事業のノウハウ】
4:本省=運輸局、運輸局同士、有識者とのつながり【人材ネットワーク】
制度、補助金、プレイヤー、パートナー(伴走者)が複雑に絡み合う地域公共交通政策においては、地方運輸局が持つこれらのノウハウを生かせる場面がたくさんありますから、自治体の皆さんには最大限活用いただければと思います。
<編>:地方運輸局という組織を「うまく使う」といっても、どうすればいいのでしょう?
<新>:まずは、運輸局の持つ1~4のどのノウハウに期待しているかを伝えていただくことです。それによって、得意な部署・職員にアクセスできる可能性が高まります。
また、せっかく相談をいただいても、何に取り組もうとされているのかという概要が分からないと、その場でできるアドバイスにも限界が出てしまいますから、どういったものでも構わないので、何らかの資料を手元に用意した上で話しかけていただけるとありがたいです。
例えば、そもそもどのように進めたら良いのか、地域公共交通計画をどういったビジョンで取り組んでいけば良いか、といった、大きな方針に関する内容について意見交換をしたい場合には、交通企画課・支局(企画調整担当)にお声かけいただくと、ざっくばらんにでも、議論相手になることができます。「相談」という形に限らず、意見交換をしたい、というフランクな形でも良いので、気軽に連絡してもらえればと思います。
運輸局・支局には、フットワーク軽く、現地に赴くことをポリシーとする職員も多くいます。現地視察しながらの意見交換という形もウェルカムです。
このほか、自治体と国との連携方法についてもお話できるかと思います。例えば、交通事業者との調整に先だって運輸局職員と会話して予備知識を得ておくことも一つかもしれません。また、地域の皆様に自治体ではなく国からメッセージを伝えることでより理解が得やすいなどの場面があれば、私たちをうまく「使って」いただくことも手です。
誰にどこで声をかければ良い?
<編>:この人に聞くと良い情報がもらえるという裏技みたいなものありますか? 読者が我々に期待しているのはこういう質問だと思います(笑)。答えづらいかもしれませんが。
<新>:基本的にどの人も真摯に仕事をしているので、情報屋みたいな人はいませんが、強いて言うなら、その業務を担当して2年目以降の職員は過去の経験を踏まえて情報を持っていることが多いので、そういう人に相談するのは手かもしれませんね。
<編>:各運輸局ではセミナーやシンポジウムを開催されていますが、こちらにも参加すると良いことがありますか?
<新>:地方運輸局では、年間通じて大小様々なセミナー・シンポジウムを開催しています。セミナー・シンポジウムは、内容面で参考になることが多いことはもちろん、運輸局サイドとしても参加回数の多い自治体は印象に残りますので、その場で立ち話的に最新情報をお伝えしたり、アドバイスさせていただくこともよくあります。メールや文面ではお伝えしにくいニュアンスを含めて、温度感を図る機会としてもぜひ活用いただければと思います。
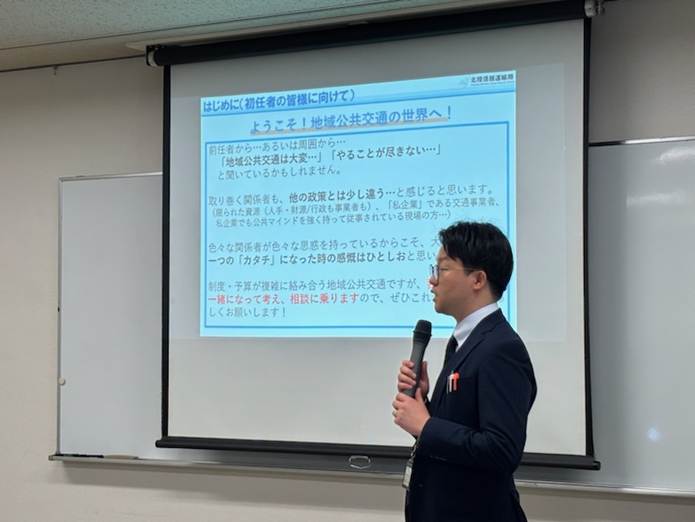

<編>:補助やアドバイスといった支援制度とは別の側面として、運輸局には、地域公共交通に関する規制官庁としての側面もあります。取組が制度上支障ないかどうか不安だということも多いかと思いますが。
<新>:地域公共交通に関係する法令では、様々な規制や要件を設けています。これらは、輸送の安全・安心を確保する観点などから設けているものですが、取り巻く状況の変化に伴い、従前は想定されていなかった取組を検討するケースもあるかと思います。新たな取組を検討するに当たって、支障になっている法令・通達の規定があれば、具体事例をもとに地方運輸局の担当者に共有していただければと思います。
現行制度でも対応できる方法がある場合には、どうすればクリアできるかといったアドバイスができます。また、本省と地方運輸局では密に情報共有・意見交換を行っていますので、何らか新たな対応が検討できないか、という点で議論できるケースもあります。規制官庁という側面はありますが、いきなり処罰するようなことはありませんから怖がらず、まずは、情報共有することを意識してみてもらえればと思います。
<編>:何事も気軽に相談してもらえれば、一緒に解決策を考えたい、というのが新倉課長のメッセージかと思いました。
<新>:もちろん、運輸局としても相談をお待ちするだけではなく、こちらから足を運んで、お話を聞きに行くことにも取り組んでいます。
最近では、「交通空白」解消のために、各地域への首長訪問などを通じて、課題の掘り起こしを行いつつ、本局・支局による伴走支援体制も構築しています。
地域公共交通政策は様々な関係者が広く関わる難しい政策分野です。地方運輸局も地域の皆様と一緒になって考え、取り組んでいきますので、よろしくお願いします。
<編>:3回にわたってお話しを伺いありがとうございました。と言いながら、新倉さんは6月いっぱいで北陸信越運輸局の交通企画課長から国土交通省本省へご異動になったということで、新任地でのご活躍を祈念するとともに、後任の大村さんにも引き続き地域公共交通の発展のためにご尽力いただければと思っております。