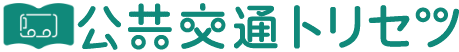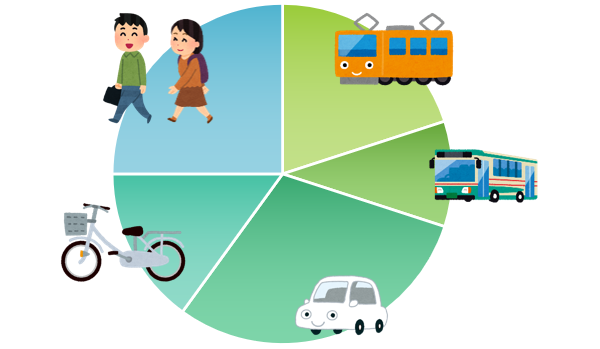減少する移動
担当:西堀泰英(大阪工業大学)
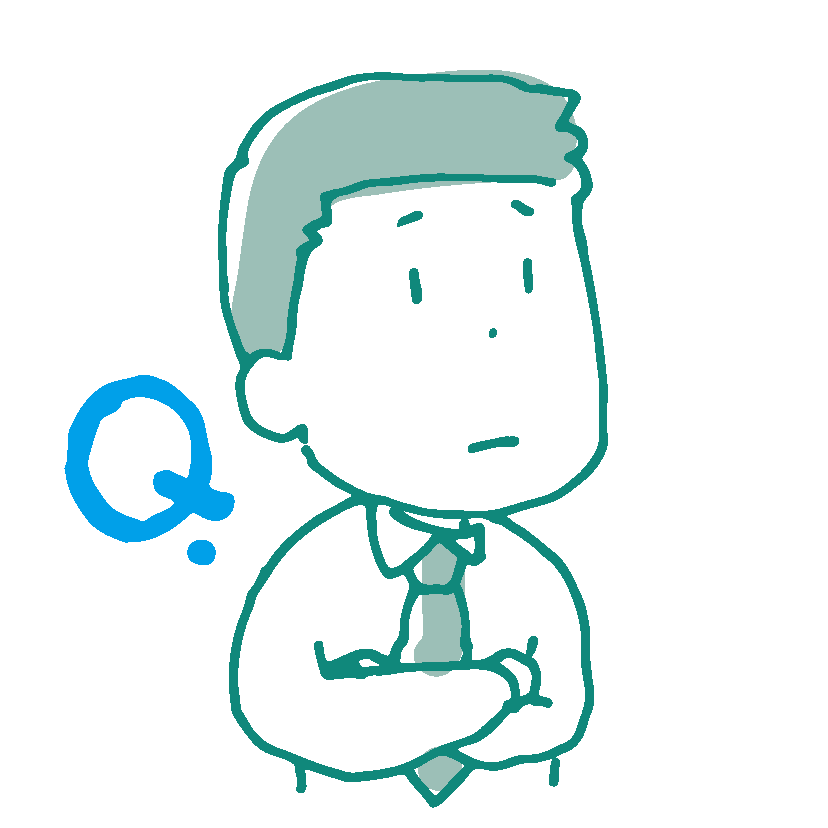
人の移動量が、コロナ禍以前の水準に戻っていないと聞きました。やはりコロナ禍の影響が残っているのでしょうか?
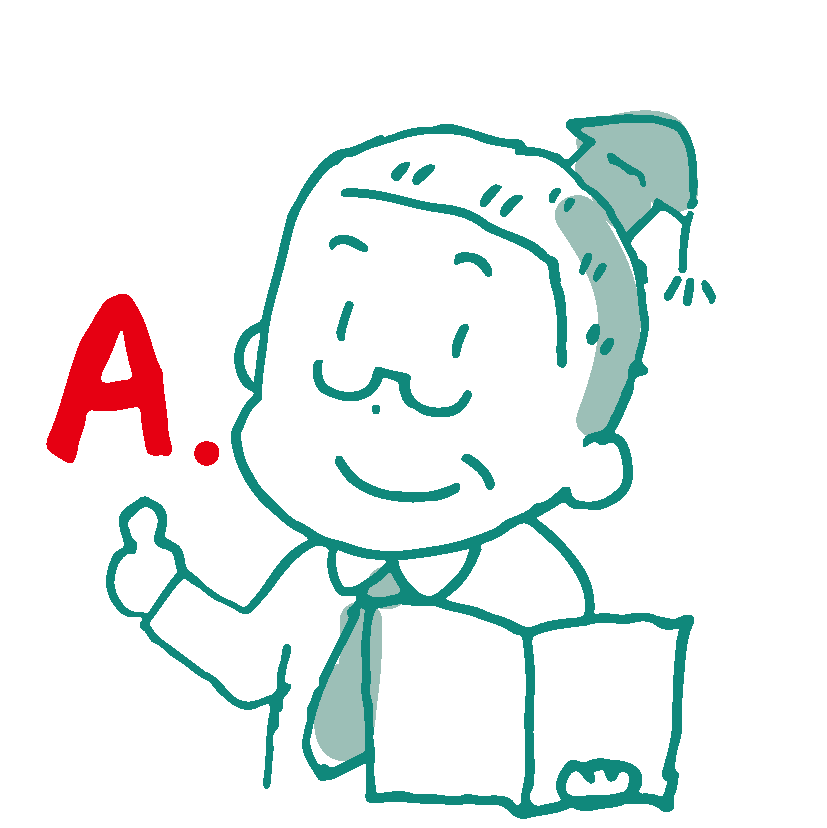
減っている理由は、コロナ禍の影響だけではありません。実は、コロナ禍以前から減り始めていました。長期的な交通需要の変化を見通した交通のあり方を考えることが求められます。
人の移動量の推移
過去の投稿(今さら聞けないパーソントリップ調査【1】パーソントリップ調査とはなんですか?)で、パーソントリップ調査(PT調査)でわかることのひとつに、「居住者の総移動回数」があることを書きました。このデータを過去にさかのぼってくらべてみると、都市圏全体の人の移動量(総生成量や総トリップ数と言います)の推移を確認できます。
図1は、三大都市圏と言われる、東京都市圏、近畿圏、中京都市圏のPT調査データを用いて、1980年前後から2020年前後までの40年間の総トリップ数の推移を示したものです。各都市圏の最新値は、東京都市圏がコロナ禍前の2018年で、近畿圏は近畿圏はコロナ禍の最中であった2020年を避けて1年遅れで実施された2021年で、中京圏はその翌年の2022年です。この図から、各都市圏において、コロナ禍の前から総トリップ数が減少し始めていることがわかります。つまり、総トリップ数の減少は、コロナ禍をきっかけとするものではないと言えます。
総トリップ数は、都市圏の居住者の移動量を表す値であるため、人口が変化すれば総トリップ数も変化します。人口変化の影響を確認するため、図2には各都市圏の夜間人口の推移を示します。各都市圏で、総トリップ数が減少する期間においても、人口は増加または横ばいであることがわかります。ただし、少子高齢化の進展により、高齢者が増加する一方で生産年齢人口や15歳未満人口が減少しています。総トリップ数の減少は、こうした人口構造の変化が関係していますが、このことはまたの機会に触れたいと思います。次では1人あたりのトリップ数について見ていきます。
図1 三大都市圏の総トリップ数の推移
出典:第6回東京都市圏パーソントリップ調査記者発表資料、第6回近畿圏パーソントリップ調査結果の最終報告、第6回中京都市圏パーソントリップ調査を基に筆者作成 特に記載がない場合以下同じ
図2 三大都市圏の夜間人口の推移
1人あたりのトリップ数の推移
人口が減っていないのにトリップ数が減っているということは、どういうことでしょうか。過去の投稿で、PT調査でわかることとして、「1人あたりのトリップ数」があることも紹介しました。どうやらこれが関係しているようです。
1人あたりトリップ数は、「生成原単位」とも言います。まずはこの値の推移を確認してみましょう。三大都市圏に加えて、全国の70都市の値(全国都市交通特性調査より。三大都市圏だけでなく地方都市圏も対象とした調査)も交えて確認します。図3に1人あたりトリップ数の推移を示します。
年によって多少の増減はありますが、長い目で見ると右肩下がりに減少していることがわかります。期間を区切って見てみます。1980年から2010年頃までをみると、1980年頃は2.5トリップ/人日を上回っていたのが、2010頃までに2.5トリップ/人日を下回り、微減していると言えそうです。そして、2010年頃を境に、減少量が大きくなっているようにも見えます。その結果、2020年頃には東京都市圏や近畿圏や全国(70都市)では2.0トリップ/人日を下回る状況となっています。
こうした変化は、ふたつの現象が重なって起きているとみることができます。すなわち、①外出する人が減っている(外出率が低下している)、②外出した人が行う移動の回数が減っている(外出者の1人あたりトリップ数が減少している)のふたつです。
図3 三大都市圏と全国の生成原単位の推移
出典:第6回東京都市圏パーソントリップ調査記者発表資料、第6回近畿圏パーソントリップ調査結果の最終報告、第6回中京都市圏パーソントリップ調査結果、都市における人の動きとその変化を基に筆者作成
なぜ移動が減っているのか
移動が減少した背景には、様々な要因が考えられますが、大きな要因としてインターネットの普及による情報社会の進展や、その後のスマートフォンの普及が挙げられそうです。
私たちの生活習慣に関係する変化として、ネット通販の普及がありそうです。これにより、買物に出かけなくても必要なものが手に入るようになりました。スマートフォンの普及は、その流れに拍車をかけたと考えられます。
また、仕事をする人たちの商習慣にも変化が起きているようです。図4は東京都市圏における2008年から2018年にかけてのトリップ数の変化を示したものです。「販売・配達・仕入・購入先へ」や「打ち合わせ・会議・商談へ」などの業務目的の移動が減少していることがわかります。従来行われていたこれらの移動が、電子メールやSNSでのやり取りや宅配サービスなどに置き換わっている可能性が考えられます。
さらに、コロナ禍の時期には「不要不急の外出抑制」の対策が取られ、在宅勤務、オンラインでの会議や講義、フードデリバリーサービスなどが一気に社会に浸透し、「ニューノーマル」と言われるようになりました。コロナ禍が落ち着いた現在も、「ニューノーマル」の生活習慣は残っています。
こうしたことが、移動が減っている主な要因と言えます。他にも移動が減っている要因には様々なものが挙げられますが、細かくなるのでここまでにしておきます。
図4 東京都市圏における性別・業務目的別トリップ数の変化
出典:第6回東京都市圏パーソントリップ調査記者発表資料を基に筆者作成
ここで、インターネットの利用について大事な指摘をしておきたいと思います。先ほど、移動が減少している要因に「インターネットの普及」があると言いました。皆さんの中には、「インターネットを多用する人は、外出や移動が少ないのではないか」と思われた方もおられるのではないでしょうか。筆者も以前(10年ほど前)はそう考えていました。でも実は、そういうわけではなさそうなのです。
少し古いデータですが、筆者らが過去(2015年)に行った調査のデータを紹介します。図5は、平日の行動(外出)回数とインターネット利用時間の関係をグラフにしたものです。これをみると、外出が多い人ほどインターネット利用時間が長い、という関係を見て取ることができます。言い方を変えると、インターネットを多く利用する人は、比較的多く外出している、と言うことができます。
図5 平日における交通行動(外出)とインターネット利用時間の関係
(ここでのインターネット利用時間は、自宅や職場や移動中の利用時間の合計値)
出典 西堀・土井ら:30〜40歳代の活動実態と個人の意識の関係分析を通じた都市交通政策に関する考察-交通行動やインターネット利用等の活動に着目して-,運輸政策研究,Vol.21,2019.を基に筆者作成
これは先ほどの、移動が減少している要因にインターネットの普及がある、という指摘と矛盾していると感じるかもしれません。ここには示しませんが、図5と同じ調査結果から、ネット通販の利用が多い人は外出を伴う買物回数も多いことがわかっています。
外出を伴う用事がインターネット利用に置き換わる場面が少なからず存在することは間違いないと言えます。しかしそれとは別に、インターネット利用が多い人は交通行動も活発であり、バーチャルやリアルを問わず人との交流や買物の機会や、情報との接点を持つ機会が多いと考えられます。つまり、インターネット普及による移動の減少とインターネットを多用する人の存在は、あまり関係がなく切り離して考えるべきと言えます。
インターネット利用と外出行動の両方が活発な人と、両方ともに活発でない人が存在しており、活動面での差が生じていると言えます。これらの結果から、筆者らは「活動格差社会」ともいえる状況が生じていると指摘しました(参考文献5))。思い込みに捕らわれることなく、データに基づいて物事を考えることが重要であることを示す事例と言えます。
今後の見通しは?
すでに日本は人口減少局面に入っており、今後は人口が減少し続けます。また、1人あたりトリップ数は、これまでの傾向をもとに考えると今後も減少すると考えられます。総トリップ数は、人口構造の変化と1人あたりトリップ数の変化がわかれば、見通すことができます。土井らは、第5回近畿圏PT調査データを用いて2030年の移動量(正確には発生集中量)を推計した結果、人口構造の変化のみを考慮した場合は2010年比で86%(14%減)に減少し、人口構造の変化と1人あたりトリップ数の変化の両方を加味した場合は2010年比で84%(16%減)と推計しました(参考文献6))。
しかし先に示したように、2010年以前の1人あたりトリップ数の減少は、2010年以降の変化と比べて小さいものでした。そこで筆者らが第6回近畿圏PTデータを用いて、土井ら6)の方法を参考にして簡便に2030年の移動量を推計した結果、人口構造の変化のみを考慮した場合は2010年比で80%(20%減)に減少し、人口構造の変化と1人あたりトリップ数の変化の両方を加味した場合は2010年比で73%(27%減)と推計されました。
これらの結果はあくまでも推計であり、今後どのように推移するかは予断を許しません。しかし確実に言えることは、こうした長期的な交通需要の変化を見通した交通のあり方を考えることが求められる、と言うことです。
ここで、将来の交通の様子を思考実験として描いてみます。大都市において、人の移動が大幅に減少したことで公共交通サービスは需要が見込める路線しか残っていない状態を考えます。
人の移動が減るので電車はガラガラかと思いきや、限られた路線しか運行していないために利用が集中し、しかも運行本数が十分でないために激しい混雑に陥っています。電車やバスが十分でないため道路は車であふれ、大渋滞を引き起こしています。自動運転車が走行する空間はないかもしれません。超高齢社会であるため、外出困難者が急増します・・・。
こんなディストピアが訪れるのはごめんこうむりたいものです。
現在の状況に戻ると、道路を含む交通インフラの老朽化、公共交通事業従事者の人手不足、公共交通事業者の経営悪化など、人々の移動を取り巻く環境は極めて厳しい状況にあります。今目の前にある問題に対処するだけでも精一杯という状況かもしれません。しかし、上のようなディストピアを招かないためにも、未来を選択できる今の段階から、将来の交通のあり方を考え、対策を実行に移していくことが重要であると訴えたいと思います。
【参考文献】
- 東京都市圏交通計画協議会:記者発表資料「総移動回数が調査開始以来,初めて減少」,2018.
- 京阪神都市圏交通計画協議会:近畿圏における人の動き,2024.
- 中京都市圏総合都市交通計画協議会:第6回中京都市圏パーソントリップ調査結果,2025.
- 国土交通省都市局都市計画課都市交通調査室:都市における人の動きとその変化,2023.
- 西堀・土井・安東・石塚・白水・中矢:30〜40歳代の活動実態と個人の意識の関係分析を通じた都市交通政策に関する考察-交通行動やインターネット利用等の活動に着目して-,運輸政策研究,Vol.21,2019.
- 土井・安東・白水・中矢・西堀:人生前半のアクティビティとモビリティの課題~若者世代(20~30歳代)の活動減少から見た社会問題に対する一考察~,土木計画学研究発表会,Vol.50,2014.