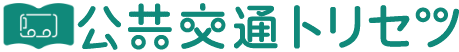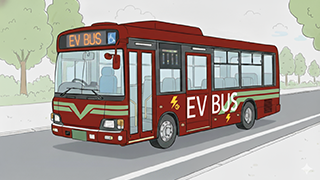担当:井原雄人(早稲田大学スマート社会技術融合研究機構)

10年前の電気バスはまだまだ使い勝手が悪い印象でしたが、最近はどうなりましたか?
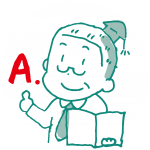
お試しで1台導入するところから、営業所単位で複数台導入するところも増えてきました。そろそろ買ってもいいかもしれません。
電気バス前史
早稲田大学で開発した電気バスが、公道で運賃をとって営業運行したのが2012年。当時は最先端な取り組みとして、国土交通大臣が視察に来たりしていました。同時期には、既存のディーゼルバスを電気バスに改造して走行する類似の取り組みがいくつかの地域でされていましたが、これはいわゆる研究開発として行われたものでした。
最初から電気バスとして開発され販売された車両の導入事例としては、2015年にBYD社の電気バスを導入したプリンセスライン(当時は京都急行バス)があります。プリンセスラインの電気バスは現在も運行を続けており、10年使い続けることができるのか?という意味では実績ができてきました。
その後、BYDに代表される中国メーカーを中心に開発が進み、国内でも2024年にいすゞ自動車によるエルガEVが発売されました。その結果、2023年には150台/年、2024年には500台/年ほどの電気バスが導入されています。バスの年間の販売台数が1万台程度ですので、まだまだ割合は少ないですが、普及が始まったといえるでしょう。
地域公共交通計画の中でも、自家用車からの公共交通への転換と電気バスの導入を組み合わせ、カーボンニュートラルの実現を事業項目として取り上げる自治体が増えてきました。こういった背景を踏まえて、今後の普及段階での問題点を改めて整理します。
普及時の問題点
これまでの電気バスの導入は、航続距離や充電時間の問題から電気バス専用の仕業を組んで走行するという形式がとられていました。これに対し、近年では車両性能が向上し、既存のディーゼルバスの仕業の一部に組み込んで走行することが可能となりました。これにより、1台のお試しの導入から、営業所単位で複数台の導入へと拡大しています。10年前は、夜間だけでなく昼間にも長時間充電をしなければならず「今までのバスと同じ使い方ができない!」と思われていました。しかし現在は、多くの路線で1日走行した後の夜間に充電し、翌朝には満充電とすることが可能です。
普及が進むにつれて新たな問題として、同時に充電する台数が増加することによる電気代の高騰を考えなければいけません。電気代は使用した電力量(kWh)にかかる電力量料金と充電設備の出力(kW)にかかる基本料金があります。電力量料金は走行した距離に応じて増加するのに対し、基本料金は同時に充電した台数の最大値(50kWの充電器で同時に10台充電した場合500kW)となります。電気バスの台数が少ない間は、1台の充電器で順番に充電すれば1台分の基本料金で済みますが、台数が増加して1台の充電器では充電が間に合わなくなると複数台での同時充電が必要になり基本料金が増加します。電力会社により異なりますが、高圧契約による基本料金は1500-2000円/kWですので、充電器が1台増えると、月の電気代がいきなり10万円上がってしまうこともあります。
この問題に対して、できるだけ効率良く充電するための取り組みが、国土交通省の交通GXでも取り上げられている、エネルギーマネジメントシステムの導入です。エネルギーマネジメントでは、充電時間を平準化させることによるコスト低減とともに、再生可能エネルギーの発電量が多い時間に積極的に充電することでCO2排出量の削減を図ります。
耐用年数の問題点
以前は5年ほど走行するとバッテリが劣化し、高額なバッテリを交換しなければならないため、さらにコストがかかるということもありました。しかし、現在ではバッテリ技術も進化し、バッテリ交換の懸念は少なくなってきました。
バッテリの劣化には様々な要因がありますが、利用側で把握するべき指標は充電サイクル数です。サイクル数は充電回数とは異なる指標で、バッテリ100%から0%まで使用し、それを満充電したら1回です。実際の運行では、100%から0%まで使用することはなく途中で充電することが多いですが、その充電回数ではなく累計で100%分充放電したらサイクル数1回と考えるとわかりやすいと思います。また、一般的に車両用のバッテリの寿命は、充電できなくなったら寿命ではなく、初期容量に比べて80%程度の充放電ができなくなったら寿命といわれ、それをサイクル寿命と呼んでいます。現在の電気バスに使われているバッテリのサイクル寿命は5000回から長いものだと1万回を越えるものもあり、これにより10年を越える走行という実績が実現しました。どれぐらい走行するかが分からないと、車両購入時に「何年使えますか?」と聞かれても正しく答えられません。1日あたりの走行距離を想定してサイクル寿命から耐用年数を考えましょう。
しかし、これでもディーゼルバスを新車で購入し、それが中古で地方のバス会社に再販され合わせて20年以上使用していたのに比べればまだ使用期間が不足しているともいえます。これに対して、現在のディーゼルバスを10年使用し、それをベース車両に電動化するレトロフィットのような取り組みも行われています。2050年のカーボンニュートラルの達成までには、まだ1,2回の車両交換が行われます。レトロフィットで前の目標を達成しつつ、10年後のさらに進化した技術の電気バスの導入をするというのも選択肢の一つです。
どこまでが国産なのか
海外を含めて様々なメーカーが電気バスの製造に参入するようになり、車両の選択肢が生まれ、お客様を乗せて走行するバスは安全第一ですので、信頼性の高い国産車をと考える方も多いと思います。
しかし、何を持って国産なのかというところには注意が必要です。一般的なクルマと違いバスを生産するメーカーは、車両の駆動部を生産するシャーシメーカーと車体や客室を生産する架装メーカーに分かれます。さらに電気バスの場合は駆動部に使用するモーターやバッテリといった部品を供給するメーカーも必要です。
これらを全て国内のメーカーが行うのが国産というイメージだと思いますが、実際は2024年に販売が始まった国産の電気バスにおいてもバッテリ等は海外製のものが使用されています。サプライチェーンのグローバル化の進んだ現在では、電気バスに限らず全ての部品が国産というものはほとんどありません。
それでも「販売しているのが」国内メーカーの方が良いという気持ちは分かりますが、海外製のものが必ずしも危険とは限りません。むしろ電気バスにおいては海外製の方が走行実績が優れる車両もあります。走行実績に加えて国内でのメンテナンス体制を把握したうえで選択することが重要です。