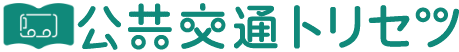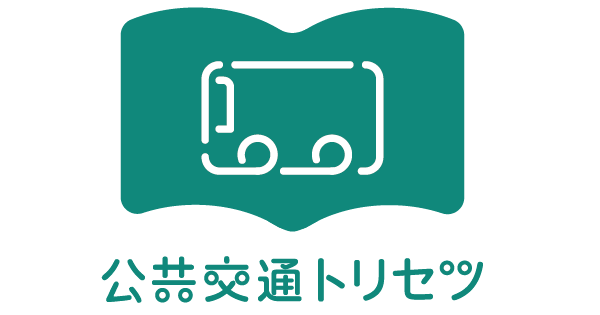担当:土井 勉(一般社団法人グローカル交流推進機構)
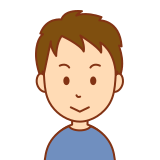
時々,交通は手段,あるいは交通は派生的需要ということを聞いたことがありますが,どんなことを表しているのでしょうか?
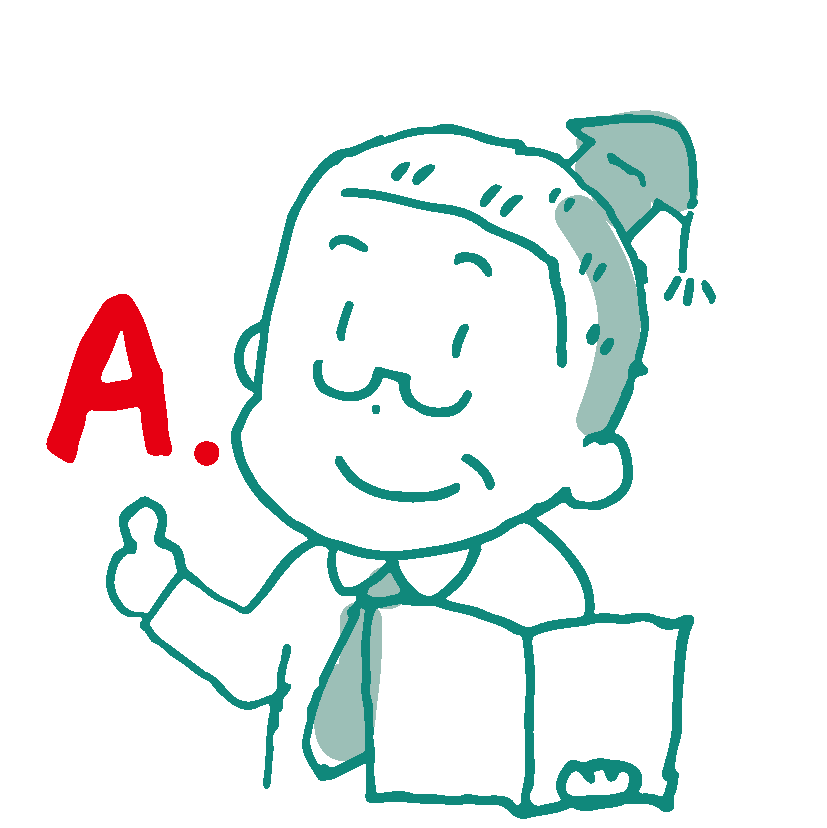
おじさん
交通には本源的需要(本源需要)と派生的需要(派生需要)の2つがあります.私たちが日々取り組んでいる交通は派生的需要が中心となります.
交通における本源的需要と派生的需要
交通政策を考える場合に,交通が主に派生的需要であることを理解しておくことが大事です.交通には本源的需要と派生的需要の2つがあります.
そこで先ず,交通における本源的需要について考えてみましょう.本源的需要の定義は,すごくシンプルで「交通すること,それ自体が目的となること」を指します.例えば,ドライブや散歩など移動そのものを愉しむ場合や,クルーズ船で旅行にいくなど移動が体験の中心になる場合が本源的需要になります.したがって交通を行うこと自体が目的になるわけです.交通を行うことが目的ですから,JR九州で運行されている「ななつ星」などは,まさに列車に乗ることが目的なので,本源的需要ということができます.
一方で交通における派生的需要とは,仕事・学校・買い物・通院・レジャーなど「様々な活動を行うために生じる交通」のことを指します.
したがって「移動すること=交通を行うこと」が目的ではなく,「移動先で何かを行うこと」が目的になるわけです.
私たちの移動需要=交通は,様々な経済活動や社会活動を行うことから派生して行われることがわかると思います.
ですから交通需要のほとんどは「派生的需要」になるわけです.
様々な経済活動や社会活動を行うことから派生的に交通が行われているので,移動=交通は目的となる活動を完遂するための手段だという言い方がされることも少なくありません.
私達が交通政策を検討する場合に,不可欠なデータを提供してくれる「パーソントリップ調査」も,交通目的ごとの移動を「トリップ」と名付けて調査を行い,通勤・通学・業務・自由・帰宅などの目的に関する様々な集計をしています.まさに,派生的需要から交通を把握することをベースとした調査方法です.
派生的需要の意味
交通計画や都市交通政策では、ほとんどの交通は派生的需要であることを前提にしています。
つまり人が移動するのは,何らかの経済的あるいは社会的な活動を行うためですから,交通政策を考える場合には,交通を見るだけでなく,その交通が行われる背景となる地域の様々な活動や土地利用の状況,人口の分布などを理解しておく必要があります.
したがって,派生的需要である交通は,地域経済が活発になると,交通需要は増加し,地域経済が停滞すると,交通需要も減少することになります.人々の外出を促し,公共交通の利用促進などに取り組む場合も,交通手段の利便性の向上だけでなく,そもそもの外出の動機(通勤,通学,買い物,通院,友人との交流,趣味などの活動など)つくりとセットで行うと,より効果が期待できるものとなります.
また,派生的需要なので,移動=交通の目的が達成できるのであれば交通手段は,移動する人にとって所要時間が短くて済む,価格が安い,乗り換えが少ないなど適切なサービスが得られるものを選択することになります.
こうした派生的需要の特性を理解しておくことで,交通政策に取り組む視点を確認することが可能となります.
交通にかけるコストは「安い方が良い」?
地域公共交通政策を考える際に,地域の方々から運賃を安価にしてほしいとの意見がでることを経験された方は少なくないと思います.
これも,本来の活動に対しては,適切な支払いを考えている人たちにとっては,交通が派生的需要であるので,できれば運賃負担は安価な方が良いという考えになるのだと考えられます.
実際には,交通に関する事業を行う場合には車両費用,車庫や駅・バス停などの関連施設の費用や減価償却費,運転士やマネジメントを行うための人件費,燃料費などが必要となります.例えば,路線バスなら1km走るためには全国平均で約500円程度が必要になります.
交通が派生的需要であっても必要となる費用を前提に利用者の人たちが負担する運賃を決めることが望ましいと考えられます.
本源的需要に関する補足
交通を本源的需要という場合に,交通の目的である通勤や通学,買い物,医療施設に行くことなどの活動そのものを本源的需要と言われる場合もあります.
ここでは派生的需要との対比で本源的需要を説明しているので,移動=交通すること自体を目的とする場合,と考えて説明をしています.その点をご注意いただければ幸いです.