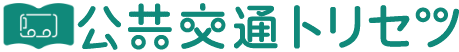担当:井原雄人(2025年8月某所で禅寺修行中)

公共交通で「お得」はなんとなく分かりますが、「お徳」とはなんですか??
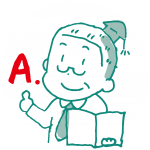
「お得」とは公共交通を利用した方が、金銭的にお得になるということですが、「お徳」とは公共交通を利用することは、人として道徳的であり、社会的に望ましいとされる行いであると意識することです。
公共交通で「お得」とは
自動車と公共交通の金銭的な負担についてよくいわれるのが、自動車の保有コスト(初期費用に加えて燃料、駐車場、車検・保険などの運行費用)より、タクシーを利用した方が安いというものがあります。土地代が高い都市部では実際にそのような事例もありますし、地方部ではいつでもタクシーを利用すればいいといわれても、タクシーの絶対数が少ないので、なかなか配車されないというような問題もありますので、これは「そういうこともあるよね」ぐらいに思っておきましょう。
ここでのお得は、公共交通を利用するごとにお得になることです。具体的には、あるお店にお買い物に行くときに、公共交通で行ったら100円割引しますというような取り組みです。これは、運賃を割引することもありますし、お店で使えるクーポンを出すというようなこともあります。どちらの場合も共通しているのは、100円というお得になるインセンティブで、公共交通の利用へ誘引することが目的といえるでしょう。
このような取り組みは多くの地域で行われていますが、思ったより運賃収入が増えないということもよくあります。これは利便性の向上と利用促進で示したように、今利用している人にとってはお得なことですが、自動車をやめて公共交通を利用しようと思うほどお得でないのかもしれません。今の利用者が割引き運賃を使うと、新たな利用者が増加しないと収入減になる場合もありそうです。
金銭的なお得で利用へ誘引するには、少しのお得ではなく無料DAYであったり、割引率の大きい政策的な割引とそれに対する自治体からの積極的な投資が必要でしょう。
公共交通で「お徳」とは
お得と違ってお徳はイメージしづらいと思います。そこでここでは、公共交通を利用することは、人として道徳的であり、社会的に望ましいとされる、徳が高まる行いであるとします。
徳が高まる取り組みは単一の行いに加えて、行いを積み上げることが大切です。「徳を積む」という表現を思い出してみれば、徳が高まる行いは1つ、1回だけ行えばよいのでなく、繰り返し積み上げることだと分かると思います。意識付けによる1回の行いではなく、意識をせずの当たり前の行いとしていくものだとイメージしてもらうと、分かりやすいかもしれません。
意識付けをして行動変容を促すという意味ではモビリティ・マネジメント(MM)に通ずるものがあります。よくあるMMのひとつとして子供向けのバスの乗り方教室があります。しかし、これはやっている側は毎年行っている継続的な取り組みと感じるかもしれませんが、子供たちにとっては1回だけの体験となります。18歳になって運転免許を取った時にはその記憶は残っていないかもしれません。
乗り方教室だけでなく、小中学校に進んだら学校MMや大人になっても職場や自治体が主体となったMMなど、繰り返し積み上げて行くことで、1回の行動変容ではなく、当たり前の行動として定着させていきましょう。
徳を積もう
そもそも「徳」とは何なのか。これを語り始めたらきりがなく、諸説ありとなってしまいます。その中での例えば、仏教用語としての徳(功徳)では、人として徳が高いということや、徳の高い行いといったものとともに、他者に対して善行を積み上げた報いとして得られる恵みとしての徳という意味合いがあります。
これを公共交通の取り組みに当てはめるならば、今の自分が得だから公共交通を利用するだけなく、今使うことで公共交通が維持され、それにより助かる人がいる。そして、その報いが未来の自分にかえってきたら、運転免許を返納した未来にも公共交通は残っているということかもしれません。(というのを期待して行動しても徳は積めないので、あくまでも自発的で当たり前な行動をしていきましょう)