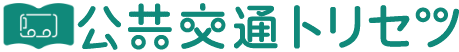担当:福本雅之(合同会社萬創社)
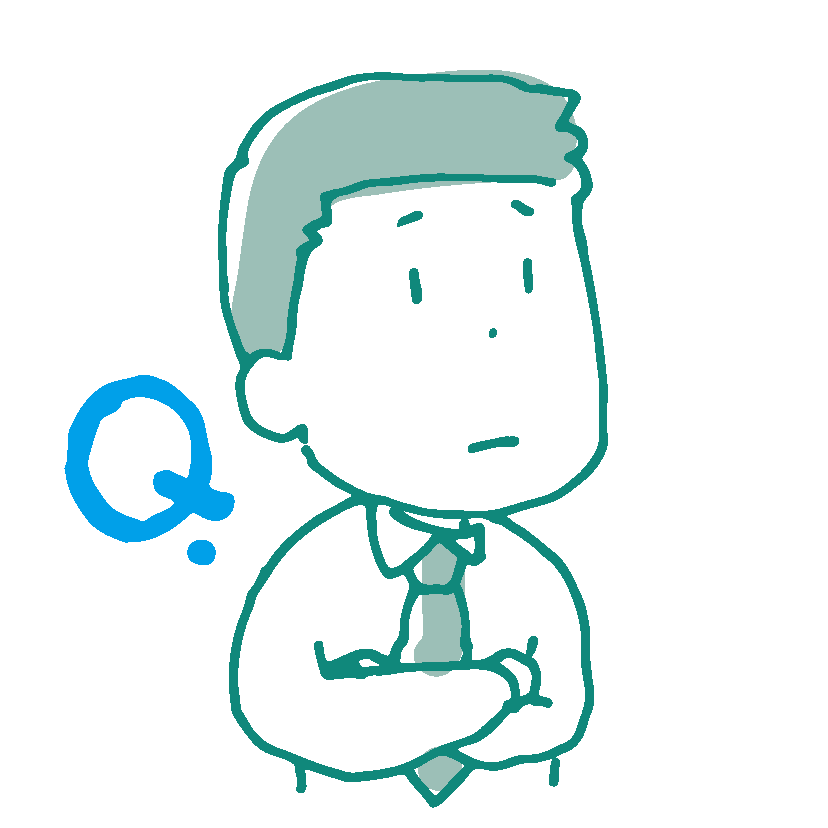
法改正で運賃協議会をやることになったけど、どうすればいいんだろう
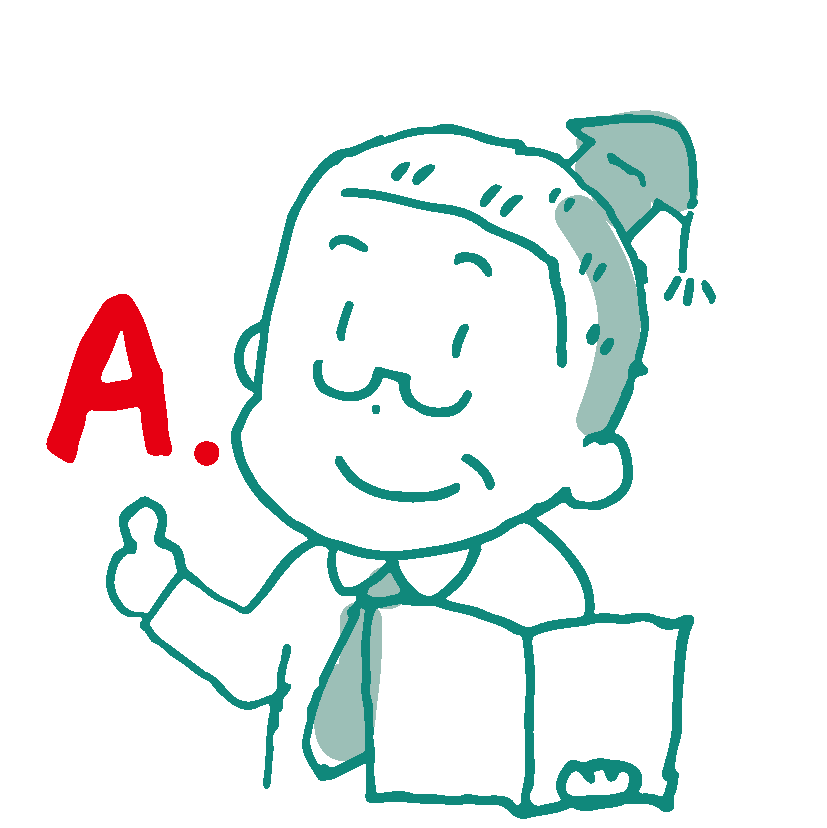
法改正の趣旨を踏まえて運用しましょう
2023年10月施行の改正道路運送法により、それまで地域公共交通会議で協議していた協議運賃については、運賃協議会という別の協議体を設置して協議することとなりました。
協議運賃とは
通常、乗合バスの運賃は上限認可制といって、バス事業者が運行にかかる原価を賄ったものに適正な利潤を上乗せして設定したものを国土交通大臣に認可申請し、認可された金額を上限として設定します。実際に設定された運賃を実施運賃といい、認可された上限運賃以下の金額として設定されます。
上限運賃や実施運賃はバス事業者が収支を賄って路線バスを運行することが前提であるため、コミュニティバスやデマンド交通など、政策的に運賃を低廉に抑えるような運賃を設定することはできません。そこで、地域の関係者による協議の結果、通常の運賃とは違う運賃を設定することができるのが協議運賃の制度です。
運賃制度については、「近畿バス団体協議会:乗合バス運賃制度について」に詳しい説明があります。
運賃協議会とは
従来、協議運賃については他の道路運送法にかかる規制と同じく、地域公共交通会議において協議をしてきましたが、2023年10月に改正道路運送法が施行され、別の協議組織である運賃協議会を新たに設置し、ここで協議をしなければならないこととなりました。
この理由について詳しく説明はしませんが、複数の交通事業者が参加する地域公共交通会議において、国の規制対象である運賃について協議することは独占禁止法に抵触する可能性があるとされたためで、運賃協議会では当該協議運賃の対象となる事業者ごとに、独立して開催することが求められています。
運賃協議会の設置
運賃協議会は、新たに会議体を設置すること以外にも、既存の地域公共交通会議の設置要綱に、①「乗合旅客運送の運賃・料金に関する事項は別に定める構成員にて協議を行う」旨の規定を追加したり、②「運賃協議分科会」や「運賃協議WG」を設置して協議を行うことを規定することでも構いません。
運賃協議会の構成員は以下の通りです(括弧内は出席者の代表例)。
- 市町村又は都道府県(担当部局の責任者)
- 当該一般乗合旅客自動車運送事業者(運賃改定の対象となるバス事業者)
- 地方運輸局長(運輸支局)
- 市町村の長(又は知事)が住民の意見を代表する者として指名する者(住民代表)
運賃協議会のポイント
先にも述べたように、独占禁止法との関係性の観点から、運賃協議会は地域公共交通会議とは別に開催することが必要です。具体的には、地域公共交通会議と連続して開催するような場合であっても別室で開催することや、地域公共交通会議のみの構成員の退出後に行うというような配慮が求められます。
ただし、運賃協議会の構成員は地域公共交通会議の構成員を兼ねることも多いため、参加者の負担を軽減する配慮が望まれます(これについては後述します)。
重要なこととして、運賃に関する協議は関係する事業者毎に行わなければならないことがあります。例えば、コミュニティバスの運行を複数の事業者に委託しているような場合の運賃協議であれば、事業者毎に協議を行わなければなりません。
運賃協議会に関する論点
運賃協議会の設置や運用は、各協議会が要綱で定めることとされています。要綱への規定の仕方についての国の考え方について、筆者が某市の地域公共交通会議の場で運輸支局の専門官に問うたところ「国としての方針は特に示していないため、協議会に任せる」という回答でした。これは本来おかしなことで、運賃という国による規制に係る方針や考え方を国が示すことなく、協議会にその運用を委ねることには問題があると思います(本省が方針を示すべきものなので、運輸支局の専門官を追及しても仕方ないと思い、そのときはそれ以上何も言いませんでしたが)。
実際にいくつかおかしな運用がなされていることを見聞きするので、ここでそれらについて問題提起しておきます。ただし、これらはあくまでも筆者個人の考えであることにご注意ください。
傍聴を認めて良いのか?
運賃協議会は、事業者間でのカルテルを防止し、公正な協議を行うという趣旨で設置されることとなったものです。このため、協議に参加する構成員は限定されています。公正な協議を行うためには、協議内容に対して構成員それぞれが独立した意思決定をすべきであり、また、どのような意思を表明する、あるいは表明したかについて、協議前、協議中、協議後に第三者から圧力がかけられることなどがないようにすべきです。
この趣旨に沿って考えれば、運賃協議会を公開で開催することは望ましくないのではないかと考えられます。傍聴者の中に利害関係者が含まれると、協議に言外の圧力をかけないとも限らないからです。
しかしながら、地域公共交通会議が公開原則の下で運用されているためか、少なくない運賃協議会が公開での開催となっています。
筆者個人としては密室での議論が必ずしも好ましいと考えているわけではありませんが、制度の趣旨を考えた場合、公開とする場合であっても傍聴者への遵守事項を徹底するなどして運用されるべきだと思います。
議決方法は多数決でよいのか?
地域公共交通会議でも運賃協議会でも、どのような条件となれば「協議を調った」と言えるのかは重要な問題です。多くの地域公共交通会議では、多数決により協議を決するという運用がなされています。もちろん、民主主義の下での多数決は、少数意見の尊重があって初めて意味をなすものですから、多数決での議決ということが規約上明確化され、少数意見への配慮がなされるという前提であれば、それに則って協議を調えるということで良いと思います。
しかしながら、運賃協議会に関しては、筆者は「全会一致」でなければ協議を調えることにならないと考えています。その理由として、構成員が国によって示されている4者であるとした場合、協議結果に服する事業者の票数は1でしかないため、事業者の経営に大きな影響を与える協議内容について、他の構成員の賛成多数により協議が決する可能性があることを懸念するからです。
実際に某町の運賃協議会であった事例ですが、多数決で協議を調えるという要綱であった上、11人の構成員のうち、7人が町職員、1人が交通事業者、1人が運輸支局、2人が住民代表というものがありました。つまり、この町として運賃を決めたいと思えば、他の全員が反対したとしても職員の賛成票だけで押し切ることが可能ということになります。
実際には、町として重要なことを決める協議会であるので、関係する職位にある町職員をすべて構成員にしただけで、悪意ある運用を考えた要綱にしたわけではないと思いますが、懸念は残ります。独占禁止法の目的に「消費者の利益確保」が掲げられていることを考えると、特定の主義主張が通りやすいような規約や構成員とすることは望ましいとはいえないでしょう。
路線やダイヤが決まる前に運賃を協議?
道路運送法改正前には、地域公共交通会議において路線やダイヤ、車両、運賃について一体的に協議を行っていましたが、運賃協議会によってこれらのうち運賃だけを別に協議することが必要となりました。
本来、路線をどうするか、ダイヤをどうするか、どのような車両を使うか、といったサービス内容に対して、どれだけの運賃を支払ってもらうことが妥当か、ということは一体的に議論するべきものですが、独占禁止法との関係で分かれてしまったものは仕方ありません。
ただし、地域公共交通会議の場において、運賃について「協議」をすることはできなくなりましたが、「議論」「意見交換」をすることまでは禁じられていません。このため、地域公共交通会議の場において今まで通り、路線やダイヤ、車両、運賃について意見交換や議論をした後、運賃を除く部分について協議を調え、運賃だけは運賃協議会での協議に委ねる、というやり方がよいと考えています。
ところで、とある地域公共交通会議でこのような経験をしました。会場である会議室に行くと、隣の会議室に「運賃協議会」という貼り紙がしてあり、地域公共交通会議の開始30分前からの時間が案内されています。この日の地域公共交通会議では、コミュニティバスの路線見直しの協議が予定されていましたので、それに関する運賃協議を地域公共交通会議に先だって行っていた、ということです。
このことが意味することは、地域公共交通会議で協議が整うかどうかもわからない、場合によっては事務局案に大きな修正が入るかもしれない路線やダイヤ、車両について、いくらの運賃を取るべきかを先に決めてしまうという、ものすごく不思議なことをやっていることになります。もし、地域公共交通会議においてサービス内容が大きく変わって、運賃が安すぎる、あるいは、高すぎるようなことになったらどうするつもりなのでしょうか。
先に運賃協議会を開いたこの市の事務局の考えとしては、両方の委員になっている方の負担を減らすためには、先に少人数の運賃協議会を開き、その後で地域公共交通会議に合流してもらう方が良いだろうという善意による配慮だとは思うのですが、やはり、サービスが決まる前に値段が決まるのはおかしく、地域公共交通会議の後に運賃協議会を手短に実施するなど、別の形での配慮の仕方があるのではないかと思います。
ちなみに、某運輸支局の方に聞くと、地域公共交通会議に先立って運賃協議会を開催するのは「差し支えない」との回答でした(運賃協議会にも出席しているのだから当然の回答ですが)。でも、筆者は変だなぁと思っています。
運賃協議会構成員に配慮した開催方法
ではどのような配慮の仕方があるのか。実際に行われている例をいくつか紹介しましょう。
地域公共交通会議終了後に運賃協議会を連続開催
一番多いのがこれです。地域公共交通会議が終わった後に、運賃協議会の構成員だけに残ってもらい、地域公共交通会議で運賃以外について協議の調った内容についての運賃部分についての採決を行うものです。すでに説明を受け、議論をしてきた内容ですからコンパクトに協議を進めることが可能です。
運賃協議会構成員のみに表決書を配布
地域公共交通会議において、路線、ダイヤ、車両というサービスと運賃を一体で議論した上で、サービス部分である路線、ダイヤ、車両について採決して協議を調え、運賃の協議については、運賃協議会の構成員のみに「表決書」を配布しておき、地域公共交通会議終了後に評決内容を記載して提出してもらうやり方としているところがあります。
このやり方であれば、どのような意思表示をするのかについて他者の影響を受けることを排除できますし、同じ協議内容を運賃協議会でもう一度説明されるというような二度手間も回避できます。ただし、地域公共交通会議の中で運賃に関する意見交換が不十分である場合には、この方法は不適切と言えますので注意が必要です。
おわりに
運賃協議会については、筆者も疑問に思うところがたくさんありますが、国土交通省が確たる方針を示していないので手探りでアドバイスをしているところもあり、ここに書いた内容が自信を持って正しいとは言い切れません。事例を積み重ねていく中で望ましいやり方を探っていきたいと思います。
道路運送法の改正による協議運賃についてのもう一つ大きな変化として「公聴会の実施」が求められるようになったという部分も挙げられます。こちらについては、別の機会に取り上げられればと思います(期待しないでお待ちください)。
なお、読者の皆さんで運賃協議会を実施しなければならない方がいらっしゃいましたら、この記事はあくまでも筆者の個人的な見解ですので、運輸支局に相談の上、問題にならないやり方で進めてください。