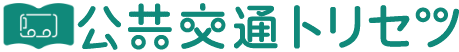担当:北川真理(株式会社計画情報研究所)
土井 勉(一般社団法人グローカル交流推進機構)

子連れ、特に小学生以下の子供連れのバス・鉄道利用って荷物も多くて大変そう。
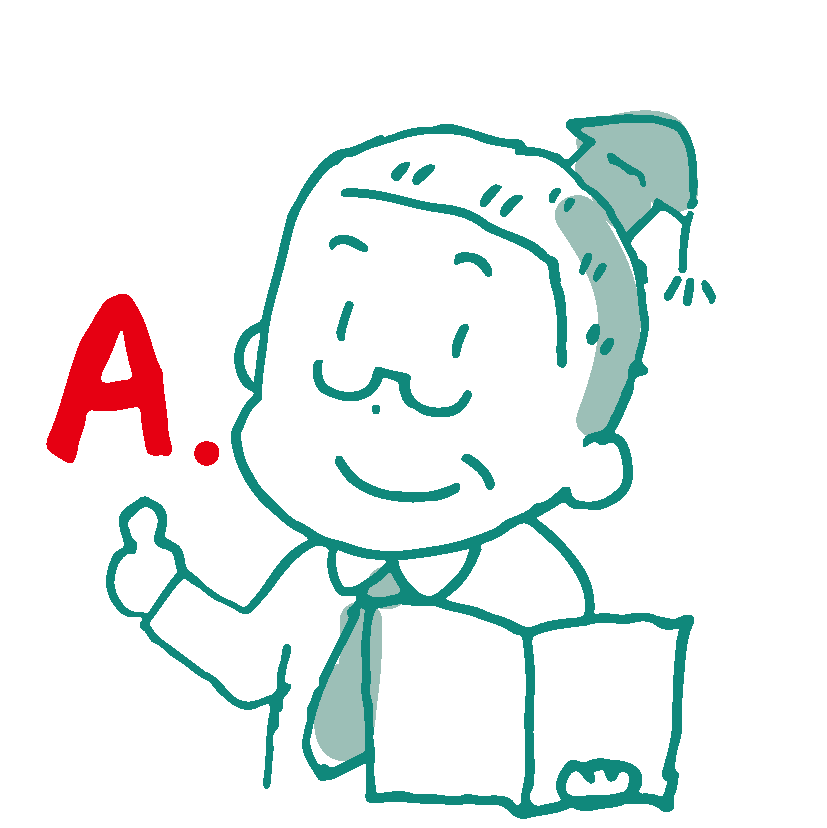
大変だけど、移動中は席を替わってくれる親切な人たちも多いので、意外に安心なのです。ただ、複数の子どもがいる場合の運賃支払がなかなか困難な場合があります。こうしたハードルが低くなると、もっと公共交通が使いやすくなるのですが…。
子連れの場合の公共交通利用にはハードルが一杯
電車やバス、それに公共の場で赤ちゃんが泣き出すことは仕方がないことです。多くの人たちもわかっていることですが、泣いている赤ちゃんの親は大変です。そこで、パニクったりしないように、京都府では「WE ラブ赤ちゃんプロジェクト」として、周囲の人たちがあたたかく見守るプロジェクトに取り組まれています(図-1)。

子どもたちを公共の場に連れていく場合の様々な問題に加えて、バスや鉄道を利用する場合には、さらに幾つかの問題があります。
幼児の場合はオムツや着替えなど荷物が多くなります。それだけでもストレスです。さらに、複数の子どもがいる場合は、当然のことですが、動き回る子も出てきたりします。もうパニックになりそうです。
それなら、無理をして子どもを連れて公共交通を利用せずに、自動車を利用した方が良いという意見もあります。しかし、誰もが自動車を使うことができる状況ではありません。それに、子どもたちにも、小さな時から公共交通の利用に馴染むことを考える親も少なくありません。
幸い、移動中については座席を譲ってくれる人たちも多くて、安心して移動することができます。
ただ、運賃支払の時に大きな問題がでてきます。
運賃支払の際の問題
通常は、保護者1名につき、小学生未満の子ども(ここでは小学生未満の子どもを「未就学児」ということにします)2名は無料になることが多いようです。しかし、未就学児の子どもが3名いる場合は、1名は子ども運賃(通常は大人の半額)を支払うと定められていることが多いようです(事業者のホームページを確認すると京都市交通局、東急、都営などなど)。
そうすると、3名の未就学児を連れて乗車している際には、降車の時に、1名分の子どもの運賃を支払うことになります。
大きな荷物を持ち、自分の運賃を支払い、さらに運転手さんに、2名は無料の確認をして、3人目について子ども運賃を支払うために、財布から小銭を出して支払うことになります。この一連の動作を、勝手に動き回る子どもたちに下車を促し、周辺の安全を確認しながら降車することになります。
これを公共交通、特にバスを利用する場合、毎回行うことになります。
こうしたことが、とても大変だと想像いただければ幸いです。それでもバスに乗車を続けている人達が確実にいるわけです。
こうした移動をしている人たちの疑問は「なぜ、3人目から有料になるのか?」ということです。それに、頑張ってバスで移動している家族の3人目から1人分の小児運賃を収受しても、交通事業者の旅客収入に大きな影響を及ぼすようなものではなさそうです。
3人目も無料にできないのでしょうか。
未就学児の運賃の無料人数は変更可能
実際に名古屋市交通局では、2018年5月1日から幼児を1歳以上6歳未満と定義して「大人もしくは小児(小学生)に同伴された幼児は4名まで無料」として、これまで幼児2名まで無料だったやり方を変更しています。
そんなことができるんですね。
国土交通省が告示している「一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款」では第24条で「旅客(6歳未満の小児を除く。)が同伴する1歳以上6歳未満の小児については旅客1人につき1人を無賃とし、1歳未満の小児については無賃とします」としています。これだと保護者1名につき1歳以上6歳未満の小児1名が無料になります。
ただ、この運送約款は道路運送法の11条で「公衆の正当な利益を害するおそれがないものであること」を満たせば、認可を受けて変更できるので、無料扱いの人数を標準運送約款より多くするといった利用者に有利な改正は特段支障なく改正できるようです。
利用促進と運賃について再考しませんか
ということで、皆様に関わりがある鉄道、路線バス、コミュニティバスなどの運賃について、小児運賃や未就学児の扱いについてご確認をいただき、機会があれば皆様の地域に相応しい制度としていくことなどのヒントにしていただければ幸いです。
地域公共交通の利用促進、あるいはドライバーの雇用を拡大するためにも、鉄道、バスなどの利用体験は極めて重要なことになります。頑張って利用されている人たちが少しでもストレスなく移動でき、利用の経験を増やしていくことができればと思います。
なお、3人もの未就学児がいる家庭って、そんなに多くありませんが、0ではありません。双子の出産の後、2年後に子どもが生まれると、ここで言っているケースに該当することになります。こうして考えると結構多くのケースがありそうです。
今回のトリセツの記事作成については、3児のお母さん方から多くの意見をいただきました。また、運輸局のご担当の方にも、運送約款などのご示唆をいただきました。多くの皆様、有り難うございました。皆様に支えられた記事なりました。