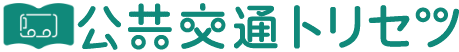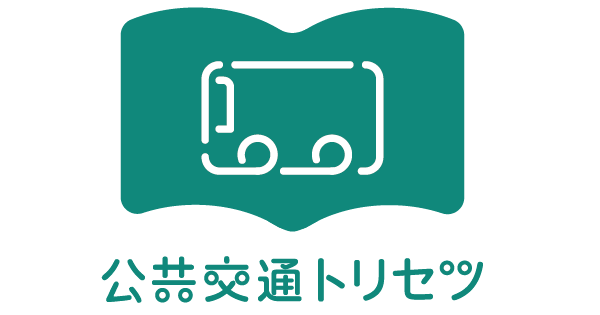思ったように利用が伸びないなど,うまくいっていない運行の見直しは,直ちにやるべきでしょうか?できれば数年後にやってくる当初設定していた見直し時期まで変更せずそのままにしたいのですが….
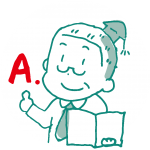
運行主体や担当者が「うまくいっていない」と認識したのであれば,見直しに向けて動き出すべきです.そのためにも,運行を始める前に「うまくいっていない」と判断する基準を設けておくことや,見直しの可能性があることをあらかじめ周知しておくことも大事です.
期待したほど利用がない・・・
運行計画を検討し,関係者が合意をして運行を始めた地域公共交通サービス.期待通りに利用されることを願うのは当然のことです.しかしながら,期待したほど利用されないことも少なからず起きているようです.
ここで,期待通りに利用されているかどうかを評価するには,「目標値」が設定されていることが重要です.目標値を設定せずに地域公共交通サービスを運行している事例も少なからず存在するようです.目標値がないと,運行の良し悪しを評価できず,漫然と運行し続けることになりかねません.地域公共交通サービスを運行することで地域が目指す姿に基づく目標値を設定することが重要です.
さて,期待通りに利用されていない場合に,運行主体はどう対応するべきか悩むことになります.「運行開始後間もないのに変更すると,うまくいっていないことを自ら宣言するようで批判を受けないか心配」「せっかく関係者が合意したものをすぐには変更しにくい」「見直すにも変更手続きに時間と労力がかかる」など,見直しすることをためらう理由には事欠きません.対応に悩む担当者の心情も理解できます.
しかし,期待したほど利用がないことや,想定した利用者からの利用が顕在化しないことなど,目標とした状態に届いていないことに運行主体や担当者が気づき,「うまくいっていない」と認識したのであれば,直ちに見直しに向けて動き出すべきです.以降では,直ちに見直すべき理由や,見直しする時の留意点,見直しをしやすくする準備について述べます.
直ちに見直すべき理由
地域の貴重な資源の浪費につながる
地域公共交通サービスは,地域住民等の移動を支えることを期待されています.その機能が期待通りに発揮されないことは,地域住民等のお出かけの機会を少なからず失っていると言えます.また,その運行には税金等の費用が投入されています.そして,人手不足が悲鳴のように叫ばれる現在,貴重な人材である運転手を雇って運行されています.
このように地域の貴重な資源を投入して運行している地域公共交通サービスを,期待される機能が発揮できないままにしておくことは,これらの資源を浪費しているとも言えます.
今困っている人は次の見直しまで待てない恐れ
さらに,現在お出かけに困っている人は,見直しが行われた後の将来も同様に困っているとは限らないという問題もあります.例えば,お出かけに困った人が親類の送迎を受けるようになりそれが定着することが考えられます.送迎は「送迎交通の意味と対応策を考える(Ver.2)」にもあるように,良い面だけでなく,個人にも社会にも悪い面があります.
他にも様々な状況が考えられます.親類等を頼って地域の外に転居してしまうことがあるかもしれません.お出かけをあきらめて生活の質が低下しそれが定着することも起こりそうです.場合によっては,次の見直しまでに不幸にも他界される方もおられるかもしれません.
見直しによりお出かけできる人が増える機会を逃してしまう
地域公共交通サービスが「うまくいっていない」ことに気が付くということは,何らかの問題が起きていることに気付くことでもあります.せっかく気づいた問題を見て見ぬふりをすることは,貴重な改善の機会をみすみす逃すことになります.
反対に,この機会を逃さずにサービスの問題点を点検して改善を行うことができれば,利用者が増えることにつながることが期待できます.さらに,見直しを行う作業に地域の住民や利用者にも参加していただくことで,地域の住民や利用者が地域公共交通サービスの運行に主体的に関わるようになることも期待できるでしょう.
期待した利用がない原因を考える
見直すべきであることがわかったとしても,では一体どうすればいいのかわからないことがあるでしょう.そんな時は「うまくいっていない」と認識したことを中心に,サービス内容が地域,あるいは利用者のニーズを満たしているか,ミスマッチしていないかを今一度点検してみるとよいでしょう.
地域公共交通サービスの内容は,「路線・系統,バス停・乗換・ターミナル・駅,ダイヤ(頻度・所要時間・接続),運賃,車両,情報提供」(公共交通が提供する6つのサービスとは何でしょうか?)であることが,過去のトリセツ記事にも紹介されています.これらを元に,地域や利用者のニーズとサービスがミスマッチしていないか考えてみるとよいでしょう.
例えば,次のようなことが起きている可能性が考えられます.
- 行きたいところに行けない(目的地,経路のミスマッチ)
- 駅やバス停が便利に使えない(事業者都合と利用者ニーズのミスマッチ)
- 利用したい時間帯に運行していない(運行時間帯,頻度,ダイヤのミスマッチ)
- 運賃負担が重くて利用できない(運賃のミスマッチ)※特に通学者
- 車両が満員で乗車できない(車両,ダイヤのミスマッチ)
- サービスの存在が知られていない(情報提供のミスマッチ)
- サービスの利用の仕方がわからない(情報提供のミスマッチ)
一度決めたサービスを見直すことは,簡単ではないことも少なくないかもしれません.そんな時は,「うまくいっていない」と認識したことを,なぜうまくいっていないのか,どうすれば問題を改善できるのかを検討されてはいかがでしょうか.また,例に挙げたことの中でも下のふたつ(情報提供のミスマッチ)は,比較的取り組みやすいものと言えるでしょう.
見直しをしやすくするために
提供したサービスの内容が,ころころと変更されることは望ましいこととは言えません.だからこそ,地域公共交通サービスの運行計画は,入念に検討して策定することが重要です.まずは地域のニーズに合った地域公共交通のサービスを,データとファクトに基づいて設定し,実証運行から始めることがよいでしょう.
しかし,いくら入念に運行計画を検討しても,うまくいかないことが起こる場合もあります.その場合に,サービス内容の見直しをしやすくするために,ふたつのことを提案します.
ひとつは,「うまくいっていない」と判断する基準を設けることです.運行開始時に見直しの基準となる「目標値」を設定し,それを地域の住民や利用者等の関係者と共有しておくことが大事です.そして,見直し基準を下回った場合の対応策をあらかじめ決めておくとよいでしょう.
もうひとつは,運行開始の段階において,見直しの可能性があることをあらかじめ周知しておくことです.こうすることで,いざ見直しを行うとなった場合に,批判を抑えることや,見直しの際の合意形成に役立つことが期待できます.
こうした工夫によって見直しを行うことになれば,見直し作業の中で,どうすれば期待通りの利用を達成できるのかを地域住民の皆さんと相談することや,実際にどのような人たちが利用しているのかを把握することで,より望ましい仕組みに改善することにもつながります.
これらの取り組みを通じて,運行主体だけが汗をかくのではなく,地域住民の皆さんの関わりも増やしていくことも重要です.そうすることで,地域の住民や利用者にとってより良いサービスに少しずつでも近づけていくと,年数を重ねることに期待通りの目標に近づく事例もあります.このように運行を地域のニーズに合致したものに見直していくことが,地域公共交通サービスを運行する際に求められる姿勢であると考えます.