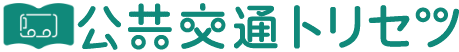今さら聞けないパーソントリップ調査【3】(最終回)

コロナ禍は過ぎ去ったけど人口減少や高齢化が進んでいる中で,都市や地域における人の動きはどうなっているんだろう・・・
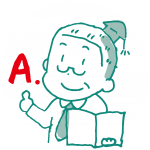
おじさん
人や社会の変化に伴い,人の動きも変化しています.思い込みではなく,データを確認して現状を認識し,それに基づいた判断を行うことが求められます.
変化の激しい時代に求められる事実の確認
地域の交通のあり方を考える際,過去の経験や思い込みが現在の状況とズレていると,誤った判断をしてしまうことになりかねません.まずは現状をしっかり認識することから始めた方が良さそうです.
今回は,シリーズ「今さら聞けないパーソントリップ調査」の3回目として,パーソントリップ調査結果の紹介を兼ねて,人の動きの意外(私にとって意外)な実態を取り上げ,現状を認識することの重要性を確認したいと思います.
人の移動に関するファクトチェック
ここでは,コロナの影響がまだ収束しきっていない2021年に行われた,第6回近畿圏パーソントリップ調査の結果を取りまとめたパンフレット(資料1)の中から興味深い結果を取り上げます.皆さまの認識が現状と合致しているかどうか,チェックしていただければと思います.ここで扱うのは近畿圏の実態ですが,近畿圏以外の地域の方もぜひチャレンジしてみてください.
まずは,下の4つのことについて,はい・いいえで答えてみてください.答え合わせは次章で行います.
- 2021年の出勤トリップ数※1は,2010年と比べて減った?
- 2021年の鉄道分担率※2は,2010年と比べて小さくなった?
- 85歳以上の高齢者は,運転免許をすでに返納した人よりも,持ち続けている人の方が多い?
- 郊外部のバス利用は,高齢者のお出かけ利用が大半?
(郊外部:人口密度500人/km2未満の地域.図1の白色の地域)
※1:出勤目的のトリップ(移動)の回数のこと.
※2:全トリップに占める鉄道利用トリップの割合のこと.構成比とも言う.
図1 近畿圏の地域分類(出典:資料1)
人の移動に関するファクトの確認
それでは答え合わせをします.
- 2021年の出勤トリップ数は,2010年と比べて減った? 答え:いいえ
- 2021年の鉄道分担率は,2010年と比べて小さくなった? 答え:いいえ
- 85歳以上の高齢者は,運転免許をすでに返納した人よりも,持ち続けている人の方が多い? 答え:いいえ
- 郊外部のバス利用は,高齢者のお出かけ利用が大半? 答え:いいえ
皆さまの認識は,どれくらい現状と合致していたでしょうか?意外に感じられることがあった方もおられるかもしれません.それぞれの詳細を見ていきます.
2021年の出勤トリップ数は,2010年と比べて減った?
2021年はコロナの影響が強い時期だったことに加え,コロナ禍を機に在宅勤務が一気に広がったことから,出勤トリップが2010年と比べて減少していると思った人もおられたかもしれません.でも,図2に示すように,2010年(平成22年)の6,637千トリップ/日から2021年(令和3年)の6,695千トリップ/日に,わずかですが58千トリップ/日増えていたのです(0.9%増加).
その理由は図2をよくみてもらえればわかります.男性の出勤トリップは減少していますが,働く女性の増加に伴い女性の出勤トリップが増加しているため,全体の出勤トリップが増えたのです.在宅勤務が増加したので出勤トリップが減少したと言われることがありますが,実際には微増の状況となっています.
図2 出勤トリップの変化(出典:資料1)
2021年の鉄道分担率は,2010年と比べて小さくなった?
コロナの影響で,密になることを避けて公共交通の利用を控える動きがあったことから,鉄道を利用する人の割合が小さくなっていると考えた人もおられたかもしれません.でも,図3に示すように,約1ポイント大きくなっていたのです.
だだし,総トリップ数(ここでは発生集中量)が約90百万から77百万に約15ポイント減っているので,鉄道分担率は大きくなっても鉄道利用者は減っています.
図3 近畿圏の代表交通手段分担率の変化
(出典:近畿圏パーソントリップ調査結果を基に筆者作成)
※トリップエンド:出発トリップ数と到着トリップ数の合計である発生集中量の単位
鉄道の分担率が増えた理由を確認するため,地域分類別の状況をみてみます.
図3に地域分類別の代表交通手段構成比の変化を示します.ここでの地域分類は先に示した図1をご確認ください.都心部と都市部において,鉄道の分担率が大きくなっています(グラフの赤枠囲み箇所).トリップ数が多い都市部において鉄道分担率が大きくなったことで,都市圏全体でも鉄道分担率が大きくなったことがわかります.
都心部や都市部では鉄道の利用に対して追い風が吹いていると捉えてもよいかもしれません.このように,実態を確認することで地域によって移動の状況が異なっていることがわかります.
図3 地域分類別の代表交通手段構成比の変化(出典:資料1)
特に20~39歳の若年層に限ってみると,全ての地域分類で鉄道の分担率が大きくなっています(!).バスについても,都心部を除く地域で分担率が大きくなっています.昨今「若者のクルマ離れ」が指摘されていますが,その影響が現れているのかもしれません.
図4 20~39歳の地域分類別の代表交通手段構成比の変化(出典:資料1)
85歳以上の高齢者は,運転免許をすでに返納した人よりも,持ち続けている人の方が多い?
高齢運転者の免許返納が呼びかけられていることは知っていても,どれくらいの運転免許返納が行われているかについてはご存じない方が多いかもしれません.図5に示すように,85歳以上の高齢者に限ってみると,運転免許を持ち続けている人よりも,すでに返納した人の方が多い(!)ことがわかります.これは,筆者にとっても驚きの結果でした.
75歳以上~84歳では,運転免許を持ち続けている人が約4割います.こうした方々が85歳以上になった際に,運転免許を返納しても移動に困ることがない交通環境を確保することが重要になると言えます.
図5 高齢者の年齢階層別の運転免許保有状況(出典:資料1)
郊外部のバス利用は,高齢者のお出かけ利用が大半?
普段バスを利用しない人にとっては,極端な言い方をすると,バスは「未知なる乗り物」かもしれません.そのバスがどんな人に利用されているのかについては,さらに未知の領域のことと思います.そんなバスの使われ方を図6を用いて確認したいと思います.
図6はバス利用トリップの移動目的の構成比を示したものであり,年齢構成を正確に読み取ることはできません.しかし,郊外部で帰宅目的を除いて最も大きな割合の移動目的は登校であり,次いで通勤です.これらの目的で移動するのは学生・生徒および勤労世代であることから,多くが高齢者以外の利用であると言えます.
郊外部に限らず,バスの運行を取り巻く環境は厳しさを増しており,最近は減便や廃止となるバス路線が少なくありません.こうした動きがさらに進んだ場合に,多くのバス利用者の移動が危機に陥ることになります.特に郊外部においては,バス利用の多くが,ほぼ毎日利用する出勤や登校目的の利用者と言えます.バスは,こうした移動を支えるかけがえのない交通機関であることを認識し,これからの地域の交通のあり方を考える必要があると言えます.
図6 地域分類別のバス利用トリップの移動目的構成比(出典:資料1)
おわりに
パーソントリップ調査データを用いた,人の移動に関するファクトチェック,皆さまはいくつ正解できたでしょうか.パーソントリップ調査データは,重要な情報を提供してくれます.各種原単位や手段分担率などの基礎的な情報はもちろん,地域別や年代別の傾向,過去からの変化動向など,様々なことを知ることができます.
今回の記事は,近畿圏パーソントリップ調査の結果をまとめたパンフレットに掲載された情報のみでまとめましたが,地域別や年代別などのさらに細かい実態の把握にも使えます.ぜひ気軽に活用してみてください(使い方は,過去の記事に記載があるので参考にしてください).また,近畿圏以外の地域の読者の皆さまにとっては,自分の地域における感覚と異なる結果があったかもしれません.そんな時はぜひ,地域のパーソントリップ調査の結果を確認してみてください.
今回で「今さら聞けないパーソントリップ調査」シリーズも一旦終了となります.ご愛読いただきありがとうございました.また次回からは新たなテーマで記事を書いて参りますので,引き続きよろしくお願い申し上げます.
<参考文献>
資料1 京阪神都市圏交通計画協議会:近畿圏における人の動き,2024年3月