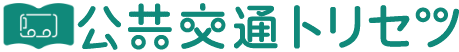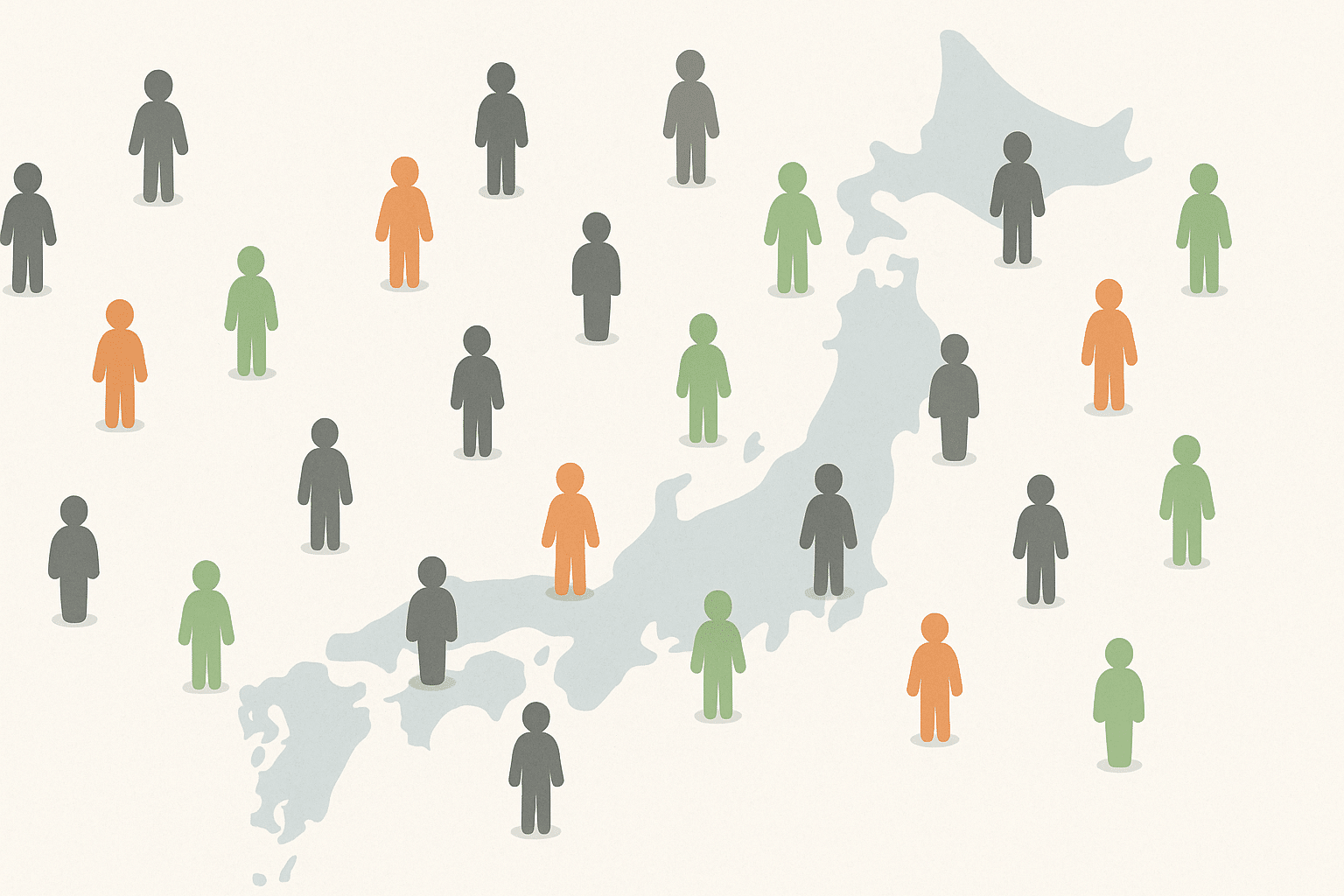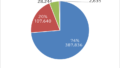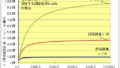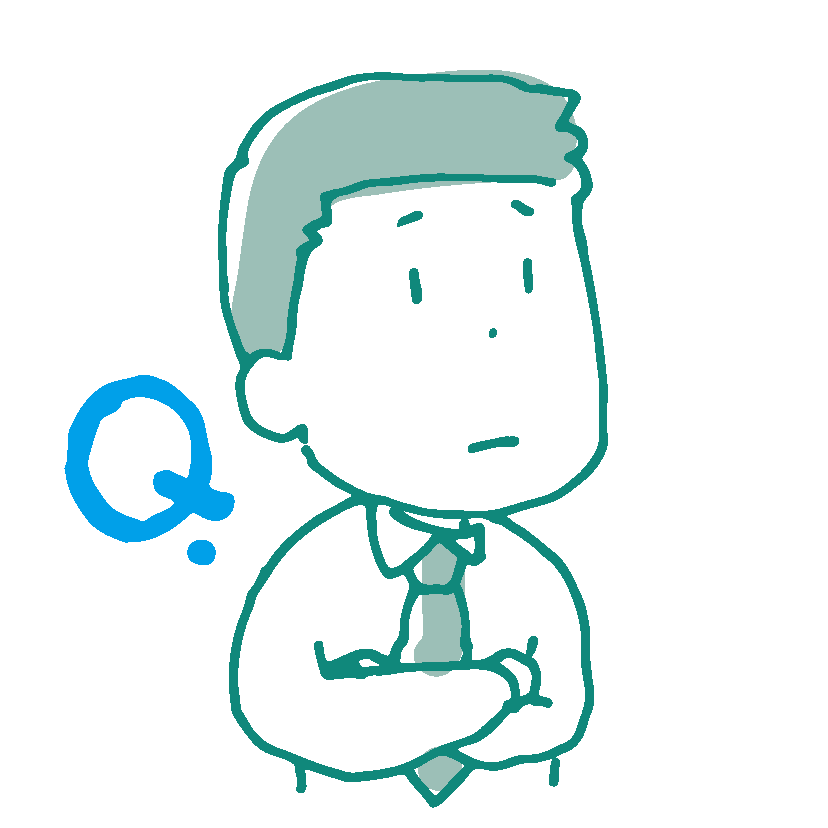
町を走るバス路線、1980年代からほとんどルートが変わっていないのですが…
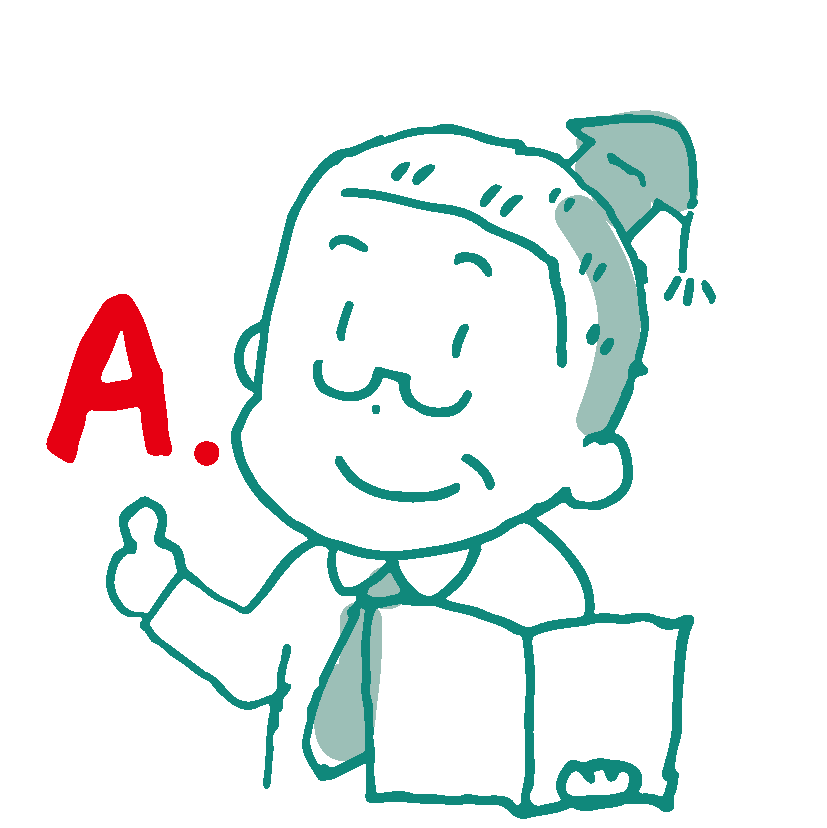
地域の実態に合わせて公共交通網も見直しが必要です。
まずは地域の人口がどう変化したか確認する方法を身に付けましょう。
人口データについて学ぼう
人口データの種類
日本国内で地域の居住者(住民)を把握する際に活用される主なデータには、5年ごとに全国で実施される「国勢調査」と、市区町村が管理する「住民基本台帳」の2種類があります。どちらのデータも地域に住んでいる住民の数を把握できますが、特徴を理解してから使う事をお勧めいたします。
| 国勢調査 | 住民基本台帳 | |
|---|---|---|
| 実施主体 (データの管理主体) | 総務省 統計局 | 市区町村(住民票管理) |
| データ種別 | 統計調査 | 行政記録(届け出ベース) |
| 更新頻度 | 5年ごと | 常時更新(リアルタイム) |
| 対象範囲 | 実際に居住している全ての人 | 届出された居住者(住民票登録者) |
| 集計単位 | 全国/都道府県/市区町村/町丁目/メッシュ | 市区町村単位(詳細非公開が多い) |
| 情報の入手性 | 統計データはe-Statなどで公開 | 個票は非公開/統計は一部公開 |
| データ精度 | 自己記入に基づくが、全世帯対象のため精度は非常に正確(更新頻度が5年に1度) | 行政サービスの基礎であり、最新かつ正確 (実居住とのズレあり) |
| 主な利用目的 | 人口算出、各種交付金算定の根拠 | 行政手続き、行政サービスの提供 |
国勢調査と住民基本台帳のズレ
実際には、国勢調査と住民基本台帳で把握される人口には差異があります。この違いは、調査時期のズレに加え、住民登録を残したまま他の地域や海外へ転出する事例があるためです。特に若年層に多く見られ、進学により住民票を移さずに都市部へ引っ越すケースや、就職による転居でも同様の傾向が見られます。また、外国人居住者も3か月以上の滞在では本来住民票の登録が必要ですが、それ以下の滞在期間の場合や、そもろも登録を行わない忘れている場合には数字に反映されません。
少し古い調査結果となりますが、2014年に全国約1800の市町村について国勢調査人口と住民基本台帳登録数の差をグラフ化した事例があるので紹介いたします。この調査結果を見ると、若年の20~24歳の年齢層において住民基本台帳登録数が、国勢調査人口より10%以上多い市町村がとても多いことが見て取れると思います。最近の国勢調査人口と住民基本台帳登録数を見比べてもこの傾向に変わりはありませんでした。データを利用する際には注意が必要です。
(統計局「統計Today No.87」より)
(統計局「統計Today No.87」より)
将来推計人口
最近ニュースを見ていると、少子高齢化や人口減少に関する話題が多く取り上げられています。こうした背景のもと、より地域に即した将来の人口変化を予測するために用いられるのが「将来推計人口」です。将来推計人口として使われるデータは一般的なものとして、国立社会保障・人口問題研究所(社人研)が、国勢調査の人口データを基にして、全国という広域から特定の市区町村や小地域単位で、年齢や性別ごとの将来人口をより細かく推計したものとなります。
多くの自治体では地域の将来像を描く際にこのデータを活用しており、学校や福祉施設の配置、交通インフラの整備計画など、具体的な政策判断にも広く用いられています。ただし、国勢調査の結果を基に全国データが分析・公表されるまでには調査から約3年のタイムラグがあり、更新頻度も5年に一度と限られている点に留意が必要です。
神戸市・静岡市など幾つかの自治体では、社人研が公表する将来推計人口だけでは、社会の急激な変化に合わせた政策立案が出来ないと判断し、独自に将来の人口推計を行っています。地域での移動問題を考える際には、自治体が独自で分析を行っている場合には、そのデータを用いた方がより精度の高い計画立案や政策に繋げられるでしょう。
<市町村が独自に将来推計を行う主な理由>
- 地域特性の反映:社人研の推計では捉えきれない地域特有の人口動向や開発計画を考慮するため
- 最新データの活用:住民基本台帳など、国勢調査より頻繁に更新されるデータを基にすることで、直近の人口変動を反映するため
- 細分化された分析:小学校区や町丁目単位など、より細かな地域単位での推計を行い、具体的な政策立案に活用するため
地域の人口変化を確認する方法
国勢調査の結果や住民基本台帳の人口データの中には居住地ごとの人口が集計されたデータがe-Statで公開されています。このデータを複数年分ダウンロードを行い経年比較を行う事で、地域の人口がどう変化したか把握することが可能です。
国勢調査では、町丁目単位で年齢・性別ごとの人口が算出されているので、経年変化を追う事で地域における人口総数の変化の他、若者の増減、男女別の増減なども確認することが可能です。ただし、集計した年度により町丁目のまとめ方が異なったり、データ項目が異なる事もあり、その点は注意が必要です。また、データは調査年度ごとにダウンロードが必要な点も注意が必要です。
上記で紹介した方法は、自分が集計したい条件で人口を詳細に把握できるため、地域の実情に即した政策立案に有効です。ただし、データの集計や分析には手間がかかる上、地域の位置関係が把握できていないと、地域全体の変化を俯瞰して見るのが難しくなります。こうした場合には、GISソフトなどを用いて地図上に可視化することで、全体像の理解に大きく役立つでしょう。
市町村単位で人口総数の経年変化を地図上で簡単に確認する方法として、都市構造可視化計画のWebサイトを紹介いたします。このWebサイトは、福岡県、国立研究開発法人建築研究所、日本都市計画学会都市構造評価特別委員会により、都市の現状を直感的に把握できるよう開発されたツールです。人口、産業構造、就業構造、商業販売額などの統計データの経年変化や、通勤・通学、買い物時の公共交通の利用状況など、多岐にわたるデータを地図上で視覚的に確認することができます。
宮城県仙台市人口総数の経年変化(1970-2015)を表示した事例
このようなツールを使うことで、地域の人口構成や分布の全体像を簡単に可視化することが可能です。しかし、公共交通施策等の施策を検討する上で明らかにすべき「地域の実情」どはどのようなものでしょうか?また、その把握ために必要なデータは手元にありますか?
地図上にデータを可視化する手法は有効ですが、利用するデータの選定は、目的に応じて見直す必要があります。なお、地図にデータを表示するためには、緯度経度や住所といった位置を特定する情報が必要なので、その点は常に意識しておこことが大切なポイントとなります。
参考資料
- 政府統計の総合窓口
https://www.e-stat.go.jp - 統計局ホームページ:統計Today No.87
https://www.stat.go.jp/info/today/087.htm - 神戸市:神戸市が独自に厳しく「将来人口推計」を分析する理由
https://www.city.kobe.lg.jp/a47946/syoraisuikei.html - 福岡県 ・ 国立研究開発法人建築研究所 ・ 日本都市計画学会都市構造評価特別委員会:都市構造可視化計画 v4
https://v4.mieruka.city/